
誰もが楽しみにしている小学6年生の行事といえば修学旅行。行き先は学校のある地域によってさまざまです。今回は、公立小学校の修学旅行について、行事の目的や、各地域ごとの行き先をまとめました。みなさんの学校はいかがでしょうか?
※調査内容は、各地域の公立小学校の一例・傾向です。同じ地域でも、すべての学校に当てはまるわけではありません。
こそだてまっぷ編集部調べ 取材・文/細川麻衣子
「修学旅行」ってどうしてあるの? 目的は?
小6の特別な行事といえば「修学旅行」です。子どもたちは学校の仲間たちといっしょに、校外に出て❝旅行❞する中で、さまざまな楽しい時間を共有することでしょう。そんな「修学旅行」ですが本来は、学校教育の延長として「歴史・自然・文化・平和などを学ぶ体験学習」、そして「社会性の育成」を目的に行われる行事なのです。
学習指導要領※1によると「修学旅行」は『特別活動』のなかの❝学校行事・旅行・集団宿泊的行事❞として位置づけられています。【修学旅行の特徴と目的】
●家庭を離れた宿泊経験・集団生活を通して、協力・思いやり・責任感を育む
●公共の場でのマナーや規律を学び、社会性の向上を目指す
●訪問先の歴史・文化・産業などについて触れることで、地域文化への理解を深める
●学びの楽しさや興味を高め、今後の学習意欲につなげる
●1泊2日~2泊3日程度が一般的いっけん観光旅行のようにも感じられる楽しい行事ですが、観光やレクリエーションにとどまらず、教育的意義をもった行事になっています。
※1:学習指導要領より

≪関連記事≫【世界が注目する日本の教育】小学校の「特別活動」について知ろう[教育評論家監修]
地域別! 訪問先の一例を紹介
修学旅行では、歴史・自然・文化・平和などを学び、それを通して社会性の育成を目指すことが目的ということですが、訪問先の傾向は、地域の特性に合わせた内容になっているようです。ここでは、地域別(都道府県を数か所ずつ)に訪問先をまとめました。
北海道・東北地方
道・県ともに広く移動距離が長いため、県内名所を基本としながらも地域によっては近隣県へも訪れる傾向があります。
●北海道:広大なので、近隣の市町村を訪れる❝道内旅行❞が最も多いようです。特に伝統的な定番コースは、自然体験や火山学習を兼ねた洞爺湖・登別・昭和新山を巡る行程のようです。
●青森県:県内で行う体験学習重視の訪問(三内丸山遺跡・奥入瀬渓流、浅虫水族館、ねぶた文化など)から、地域によっては近隣の北海道道南エリア(函館・大沼など)にも訪れることがあるようです。

●宮城県:松島や近隣の岩手県へ行くケースが多く見られます。世界遺産を学ぶ歴史学習(源義経ゆかりの金色堂など)として中尊寺、そして近年では東日本大震災の震災遺構を巡る2泊3日が主流のようです。

関東地方
●東京都:都外へ出る傾向が強く、行き先は区や市によってさまざまです。代表的な行き先は以下です。
○栃木県・日光へ
日光東照宮、華厳の滝、奥日光の湿原など、歴史と自然学習が両立した、最も定番の行き先・行程になっています。

○神奈川県・箱根へ
温泉、ロープウェイ、自然散策などを通した体験学習をメインとした行程です。
○山梨県・本栖湖周辺へ
自然環境を生かし、水辺学習や森林体験を含む行程になっています。
○新潟県・魚沼地域へ
農村・郷土文化体験を重視し、自然環境との関わりを深める学びが組まれています。
●神奈川県・千葉県・埼玉県:3県ともに主流は栃木県日光です。東京都と同じく、歴史と自然体験が学びの目的になっています。その他の行き先には、箱根・鎌倉・横浜周辺や、山梨・富士山方面の場合もあるようです。日数は1泊2日が主流で、場合によっては2泊3日の学校もあります。
中部地方
●長野県:主に県内(松本・諏訪・戸隠・上高地・善光寺など)を巡りながら、自然と文化を融合した地域理解が深まる行程になっているようです。1泊2日~2泊3日、学校によって日数に差があります。

●愛知県:愛知県は地域によって行き先の傾向に違いが見られます。名古屋市は、京都・奈良方面が最も一般的な行き先。法隆寺・奈良公園、金閣寺・銀閣寺・二条城・清水寺などを巡るようです。一方で、名古屋港水族館・レゴランド・明治村など愛知県内や近隣県を訪問する学校もあり、地域文化・自然・体験学習に重きを置いた行程の学校もあります。
●新潟県:新潟市内の小学校の多くは、佐渡島へ2泊3日することが多いようです。佐渡ならではの歴史・環境・自然とのふれあいや、離島体験を通じた自主学習が魅力です。また、隣接する福島県会津地域へ、歴史・文化体験を兼ねて訪れる学校も。

近畿地方
●大阪府:最も多いのは京都・奈良・大阪のうち1~2か所を1泊2日で巡る行程で、歴史的・文化的施設が組み合わされていることが多い傾向です。近年は、学びと体験・自由行動のバランスのため、太秦映画村や海遊館などを組み合わせる学校も増えています。また、兵庫・徳島あるいは広島・岡山方面を巡る行程もあり、さまざまです。
●京都府:京都は神社仏閣をはじめとした世界遺産が多数あることから、府内と近隣県を巡る行程が主流のようです。京都・奈良方面への歴史文化学習型が最も一般的で、東大寺・金閣寺・清水寺・法隆寺・平等院・二条城、そして太秦映画村などを巡るのが定番です。地域によっては、広島・姫路方面で平和学習として原爆ドームに、娯楽体験学習として姫路城や姫路セントラルパークなどへ行く学校もあります。

●三重県:県内の伊勢・志摩・鳥羽地域へ行くことが定番のようです。特に伊勢神宮は日本の神道の中心地。歴史や文化を学ぶことができます。他の行き先には、鈴鹿や津市周辺へ訪れる行程もあります。鈴鹿サーキットでは、モータースポーツの聖地として化学技術等を学びます。
中国・四国地方
●広島県:県内の多くの小学校では広島市内を訪れ、平和学習を行います。広島平和記念公園、原爆ドーム、広島平和記念資料館では、戦争と被爆の実態やその後の影響について学びます。さらに、実際に被爆体験をされた方のお話を聞き、戦争の悲惨さを学びます。また、広島市内からフェリーでアクセスできる宮島には、世界遺産の厳島神社があり、歴史や文化を学ぶため訪れます。

●島根県:県内の出雲大社や松江城を巡り、歴史や文化に触れる行程が主流です。近年は、隠岐諸島へ行く学校もあり、離島での自然学習が行われています。
●高知県:県外が主流で❝大阪・京都❞、❝広島・岡山❞この2つの訪問先のどちらかに行くことが多いようです。一方で、学校によっては県内で自然学習を行うところもあり、住んでいる地域によって、行き先には差があります。
九州・沖縄地方
●福岡県:近隣の長崎県で平和学習を行うのが主流です。主に長崎原爆資料館、平和公園、軍艦島デジタルミュージアム、ハウステンボス、出島跡地などの施設を訪れるようです。また、学問の神様である菅原道真公を祀る太宰府天満宮を参拝することもあります。

●鹿児島県:多くは、知覧特攻平和会館や維新ふるさと館で平和・歴史学習をします。霧島神宮・高千穂牧場・日本エアコミューター格納庫などを巡る県内の行程と、近隣県、特に熊本県の熊本城の見学や田原坂の西南戦争資料館などを巡る行程など、学校によってさまざまです。

いかがでしたか? 「修学旅行」の目的と行き先を紹介しました。地域柄がそれぞれ出ていましたね。いずれも小学校での学びを、より深められる素敵な行事ということがわかりました。多くの体験を通して、子どもたちにとって楽しい思い出と成長につながると良いですね。
この記事の監修・執筆者

未就学から中学生までの子を持つママ編集者を中心に、子どもの学びや育ちに関する様々な情報を日々発信しています!
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪










![【 “塾弁”は食中毒対策を入念に!】安全なお弁当作りのポイントとは?[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/03/pixta_61462921_S_Nqs3.jpg)
![[中学受験]入試前日と当日に親ができること【先輩ママに聞く成功&失敗談】](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/12/1-1title_01_Esxl-700x515.jpg)












![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)









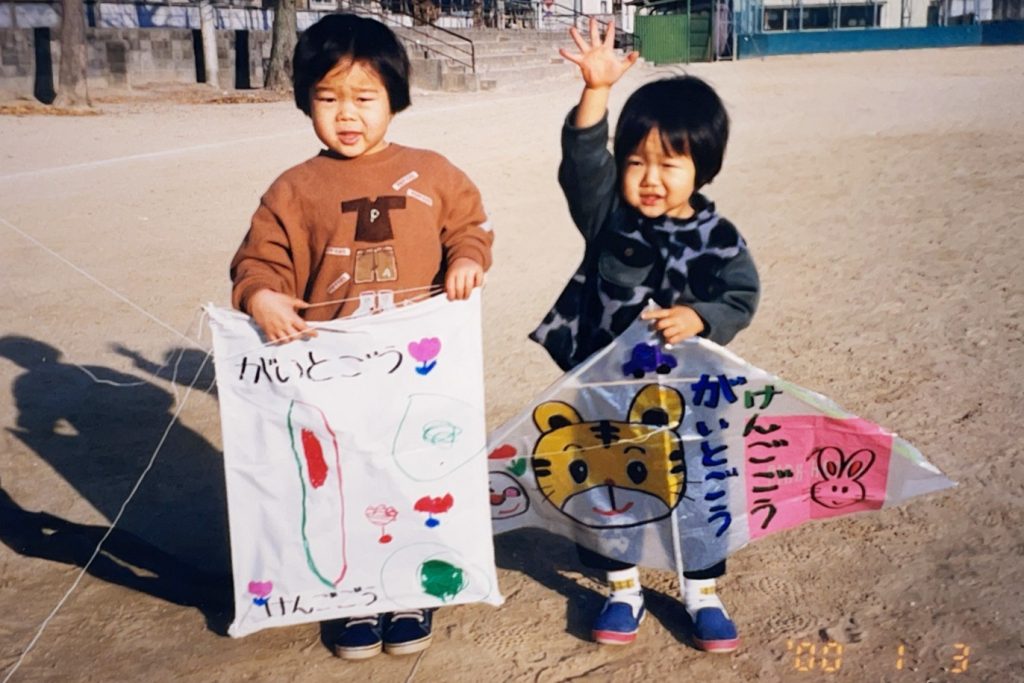


![【魚へん漢字クイズ】魚に◯で何の魚? 親子で楽しく学べる豆知識も![全8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/sakanakuizu_title_ExcK-1024x725.jpg)
