![【小4の国語】学習目標&内容と楽しく学ぶ習慣を身に付ける方法とは⁉[教育評論家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/03/pixta_123364010_M_hmDm.jpg)
4年生の「国語」は、ますます難度が上がる漢字学習をはじめ、より複雑な文章題や、ローマ字学習の応用など、さまざまな面から暗記力そして理解力・読解力などの“考える力”を求められる場面が増えてきます。
さらに、学習塾・受験塾などへ通い始めるお子さんがぐっと増える学年でもありますので、子どもたち自身が、学習環境の変化を感じ始めることでしょう。そして家庭だけでの学習フォローも、さまざまな面から難しくなってくる頃でもあります。
ここでは4年生で学ぶ「国語」の学習目標と内容、それに向けて家庭で今できることについて、教育評論家の親野智可等先生にお伺いしました。
取材・文/細川麻衣子
「国語」は全教科のなかで最も“時数”の多い教科
4年生になると3年生のときとくらべ、授業時数※1が増えます。全教科を合計すると1年間では980(3年生)→1015(4・5・6年生)に増加します。これによって子どもたちは「6時間目が増えた!」などという実感が出て、学校で過ごす時間が3年生の頃にくらべると、より長くなると言えるでしょう。
※1学校教育法施行規則に定める標準授業時数のこと。授業時数の1単位時間は45分。(参考URL:文部科学省 小学校・標準授業時数について)
この1015時数のうち、4年生の「国語」は245時数あります。これは3年生のときと引き続き同じですが、実は1年生~4年生までの「国語」は、全教科の中で最も時数が多い教科なのです。そのため、国語と並んで学習時間がたくさんありそうな「算数」でも4年生では175時数となっており、圧倒的に「国語」の方が学校で学ぶ時間が多くなっているのです。
ちなみに、3年生から4年生で時数に変化のある教科は、「理科」が90→105、「社会」が70→90となり、全体的に、より学習教科にかける時間が増えていきます。
4年生の「国語」、学習内容は?
4年生の「国語」は、これまでに学んできたことを土台に、さらに語彙力を豊かにし、言葉の使い方や表現の工夫などを、より多く深く学びます。新たに学ぶ漢字は202字です。これは6学年で習う漢字の中で最も多く、画数の多い漢字も登場します。そして3年生で始まった毛筆学習やローマ字についても継続され、より実践的な内容になります。短歌・俳句、ことわざや慣用句、故事成語などについても引き続き学習します。
小学校学習指導要領 国語編の『第1節 国語科の目標/第3学年及び第4学年』の「思考力,判断力,表現力等」の部分には、こうあります。
――第3学年以降では筋道立てて考える力の育成に重点を置いている。自分の思いや考えについては,第3学年及び第4学年ではまとめること,第5学年及び第6学年では広げることができるようにすることに重点を置いている。―― (一部抜粋し編集)
このように、3・4年生は“筋道立てて考える・まとめる”こと、そして、5・6年生に向け“広げる”ことができるように、4年生の段階では、3年生の頃よりもさらに自分の思いや考えを整理し、まとめることができる力が求められるでしょう。
【文部科学省 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説「国語編」】を参考にまとめ
※以下参考部分の表記は参考元に準じています
第3学年及び第4学年の内容(第2節より)
(「国語」の学習指導要領は2学年ごとの表記になっています。ここで表記するものは第3学年の内容も含みます)
(1)知識及び技能
日常生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに、我が国の言語文化に親しんだり理解したりすることができるようにする。
●言葉の特徴や使い方
・ローマ字の読み書きの習得(主に第3学年。)
・学年別漢字配当表※2より、第4学年で学ぶ漢字:202字
・様子や行動、気持ちや性格を表す語句の量を増し、語彙を豊かにする
・文や文章では、主語と述語との関係、修飾と被修飾との関係、指示する語句と接続する語句の役割、段落の役割を理解する
・丁寧な言葉を使うとともに、敬体・常体の違いを理解する
●情報の扱い方
比較や分類の仕方、必要な語句などの書き留め方、引用の仕方や出典の示し方、辞書や事典の使い方を理解し使う
●我が国の言語文化
・易しい文語調の短歌や俳句から、言葉の響きやリズムに親しむ
・ことわざや慣用句、故事成語などの意味を知り、使う
・漢字が、へんやつくりなどから構成されていることについて理解する
・書写では、毛筆で点画の書き方への理解を深める
・幅広く読書に親しみ、必要な知識や情報を得ることに役立つことに気付く
(2)思考力、判断力、表現力等
1・2学年で学んできた、話す・聞く・書く・読むことを基礎に、さらに筋道立てて考える力や豊かに感じたり想像したりする力を養い、日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め、自分の思いや考えをまとめることができるようにする。
(3)学びに向かう力、人間性等
言葉がもつよさに気付くとともに、幅広く読書をし、国語を大切にして,思いや考えを伝え合おうとする態度を養う。
※2 学年別漢字配当表に記されている各学年の字数
第1学年:80字、第2学年:160字、第3学年:200字、第4学年:202字、第5学年:193字、第6学年:191字、計1026字
【対策①】202字の漢字は、語源や成り立ち、都道府県を関連づけて覚えよう!
1~6年生で最も学ぶ字数が多いのが4年生の漢字です。3年生のときからさらに難度も増し、画数も最大画数20画の漢字が登場します。4年生で習う漢字の特徴としては、次のようなものがあります。
●都道府県名の漢字が頻出。独自の読み方をするものも
「茨」「媛」「縄」「潟」「熊」「香」「滋」「鹿」「岐」「阜」など
●最大画数20画の漢字が登場
「議」「競」
●同じ読み方をする漢字の使い分け方を理解
「競争・競走」「治す・直す」「期間・気管・器官」「関心・感心」「自身・自信」「校庭・高低」「辞典・事典・(時点・自転)」「起用・器用」「返す・帰す」「切る・着る」「開ける・空ける・明ける」「熱い・暑い」「別れる・分かれる」「覚める・冷める」など
【4年生で学ぶ202字の漢字】
愛 案 以 衣 位 茨 印 英 栄 媛 塩 岡 億 加 果 貨 課 芽 賀 改 械 害 街 各 覚 潟 完 官 管 関 観 願 岐 希 季 旗 器 機 議 求 泣 給 挙 漁 共 協 鏡 競 極 熊 訓 軍 郡 群 径 景 芸 欠 結 建 健 験 固 功 好 香 候 康 佐 差 菜 最 埼 材 崎 昨 札 刷 察 参 産 散 残 氏 司 試 児 治 滋 辞 鹿 失 借 種 周 祝 順 初 松 笑 唱 焼 照 城 縄 臣 信 井 成 省 清 静 席 積 折 節 説 浅 戦 選 然 争 倉 巣 束 側 続 卒 孫 帯 隊 達 単 置 仲 沖 兆 低 底 的 典 伝 徒 努 灯 働 特 徳 栃 奈 梨 熱 念 敗 梅 博 阪 飯 飛 必 票 標 不 夫 付 府 阜 富 副 兵 別 辺 変 便 包 法 望 牧 末 満 未 民 無 約 勇 要 養 浴 利 陸 良 料 量 輪 類 令 冷 例 連 老 労 録 (202字)
このように、さまざまな特徴をもった漢字を学びます。
このとき、よりラクに楽しく学習する方法は、何かに関連付けて覚えるということです。
例えば、都道府県名に使われる漢字は、絵地図やパズル、また旅行のガイドブックなどを一緒に見ながら「新“潟”県って甲信越地方なんだね~! 夏はキャンプ、冬はスキーができそう!」などと話をしながら、家族のレジャーや旅行を想像して会話しましょう。そこで実際に「新“潟”」と書いてみるなどして、楽しい会話の中で覚えていくことも良いでしょう。
これは同時に4年生「社会」の都道府県の学習にも関連づけることができるので、一石二鳥です。

また、楽しく読みすすめられる「漢字の学習マンガ」や、遊びで学べる「漢字かるた」、語源・成り立ちが説明された、読みやすい小学生用の「漢字辞典・図鑑」などを、1冊用意することも有効です。小学生用の漢字辞典・図鑑なら、小学校で習う1026字はじめ、中学で習う1110字を含めた2136字の常用漢字、さらに四字熟語なども掲載されています。この先5・6年生の国語の学習まで役に立ちますし、またこれまで習った漢字の復習としても重宝します。同じ部首の漢字も頻出するので、そのときに“なぜこの形か?”など、成り立ちを知ることで、難しい漢字も覚えやすくなるでしょう。
≪関連記事≫【小3の国語】楽しく勉強を始めるため、春休みに家庭で取り組んでおくとよいこととは[教育評論家監修]
【対策②】学習効率を上げる基盤は「読書」。家族で10分トライ!
「読書」は学習そのものに対して、とても効果的です。本を読むことで、自然と読解力や語彙力、思考力、表現力など、学習に役立つ多くの効果が得られるからです。
また、想像力やコミュニケーション能力、感性、創造力などを育むことにもつながるといわれているので、とにかく何歳になっても「読書」することは、学びを深められる良い時間と言えるでしょう。
幼児期や低学年のうちは親による読み聞かせが効果的なのですが、4年生くらいになるとなかなか難しいと感じる方もいるかもしれません。また子どもに「ひとりで読みなさい」と促しても、なかなか読んでくれないかもしれません。
そこで、お勧めしたいのが「○○家の読書タイム」といった感じで、家族全員で同じタイミングで10分間読書する、というもの。これは効き目がありますよ! 夕食後の10分間など、タイミングはご家族で集まりやすい時間帯でOKです。この時間だけは、保護者の方もスマホやお仕事はストップして、読書に専念してみてください。
家族が読書をしていると、不思議と子どもも読書するようになります。10分読むと、人は続きが読みたくなるのです! それで、読書タイム以外にもけっこう読んだりするようになるんですよ。

この「家族の読書タイム」のポイントは以下の2点です。
① 短時間でも毎日継続。習慣化する(ゼロにしない!)
勉強もスポーツもそうですが、続けることって大切ですよね。「継続は力なり」です。習慣化することで、子どもも自分から読む、ということができるようになると、この先、中学・高校などでの学びの姿勢にも良い影響があることでしょう。
② 読む本は子ども自身が選んだものを尊重する
つい物語などの本を子どもに読ませたいと思う保護者の方も多いかもしれませんが、保護者が決めてしまうことは逆効果です。また、本がそんなに好きではないお子さんの場合は、「好きなこと」にまつわる内容の本ならなんでもOKです。図鑑や人気キャラクターの絵本などももちろんOK。とにかく子どもが「好きなこと」から入り、読書を習慣化させることが大切です。
【対策③】「国語」が楽しいと思える “楽勉”を!
4年生の国語は、難しい漢字をはじめ、ローマ字・短歌・俳句・ことわざ・慣用句・故事成語など単純に筆記・暗記することから、さらに「考える」という、複雑に思考を巡らせなければならないことが格段に増えてきます。
そこで、より意識的に実践してほしい、おすすめの学び方が“楽勉(らくべん)”です。これは、ここまでにお伝えしてきた日常生活を楽しく学習に結びつける方法です。これは、今この時期の子どもたちにとってとても有効です。
4年生になると、学校の授業対策や中学受験のためなど、学習面へのさまざまな考えから、通塾を検討するご家庭も増えてくることでしょう。そのときこそ、「国語」をはじめとした勉強が“楽しい”と子ども自身が感じられる学びの場かどうかを、意識してみてください。子ども自身が楽しいと感じれば、おのずと学習意欲が増して主体的に学ぶようになるでしょう。
いかがでしたか? 4年生の「国語」は、日常生活のさまざまなことと関連付けて、楽しく学ぶことができそうですね。ぜひ、ご家庭でも取り入れてみてください。
この記事の監修・執筆者

教育評論家。本名、杉山桂一。長年の教師経験をもとに、子育て、しつけ、親子関係、勉強法、学力向上、家庭教育について具体的に提案。『子育て365日』『反抗期まるごと解決BOOk』などベストセラー多数。人気マンガ「ドラゴン桜」の指南役としても著名。Instagram、Threads、X、YouTube、Blog、メルマガなどで発信中。全国各地の小・中・高等学校、幼稚園・保育園のPTA、市町村の教育講演会、先生や保育士の研修会でも大人気となっている。
mail:oyaryoku@ka.tnc.ne.jp
Threads:https://www.threads.net/@oyanochikara
Instagram:https://www.instagram.com/oyanochikara/
X:https://twitter.com/oyanochikara
Voicy:https://voicy.jp/channel/2888
Blog:http://oyaryoku.blog.jp
㏋:http://www.oyaryoku.jp
メルマガ:http://www.mag2.com/m/0000119482.html
YouTube:https://tinyurl.com/5cj96wjk
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪
あわせて読みたい
おすすめの本
-

新レインボー小学漢字辞典 改訂第6版新装版 ワイド版
学習漢字1026字を含む常用漢字と人名用漢字・表外字約3150字、熟語は37500語収録。硬筆・毛筆手本と全画筆順つきで正しい字を書く力がつく。漢字の使い分けは豊富なイラストで解説。別冊「まんがでわかる漢字辞典のつかい方」付き。
-

新レインボー小学国語辞典・漢字辞典 最強王図鑑エディション 辞書バッグ付きセット
大人気の最強王図鑑キャラクターがちりばめられた『新レインボー小学国語辞典 改訂第7版 最強王図鑑エディション』と『新レインボー小学漢字辞典 改訂第6版新装版 最強王図鑑エディション』の2冊を専用ケースに入れたセット。最強王図鑑デザインの辞書バッグつき!
-

毎日のドリル 小学4年 漢字
やりきれるから自信がつく! 1日1枚の集中で、学習習慣が身につく人気ドリル。ドリルを進めるとキャラクターが育つ専用アプリで、勉強のやる気がアップする。小学4年で習う全漢字202字をくり返し練習できるので、漢字の力がつき語彙も増える。
-

学研の総復習ドリル 小学3年
総復習ドリルの決定版! 全学年に英語・理科・社会つき!
算数と国語の1年間の復習が、短期間に効率よくできます。「総復習テスト」「全漢字チェック」で総しあげができます。
英語・理科・社会の「さきどりプリント」と、4年で使える「えいごポスター」「都道府県ポスター」つき。








![【小4の算数】学習目標と内容、そして家庭でできるサポートについて[教育評論家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/02/pixta_49352567_M_HjJ2-700x467.jpg)



















![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)


![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-700x467.jpg)





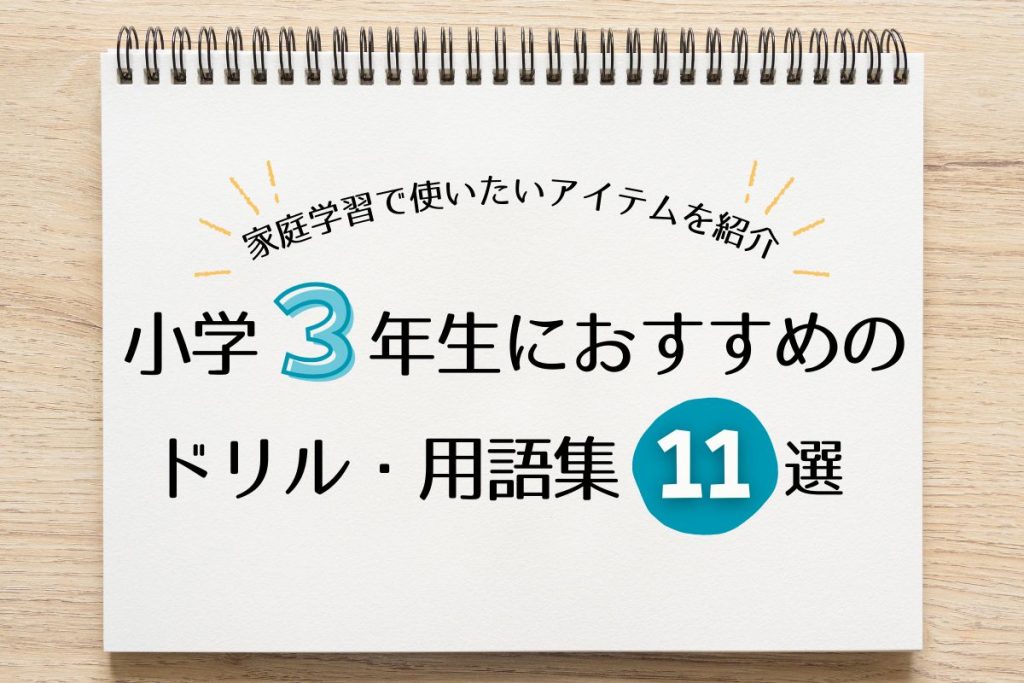
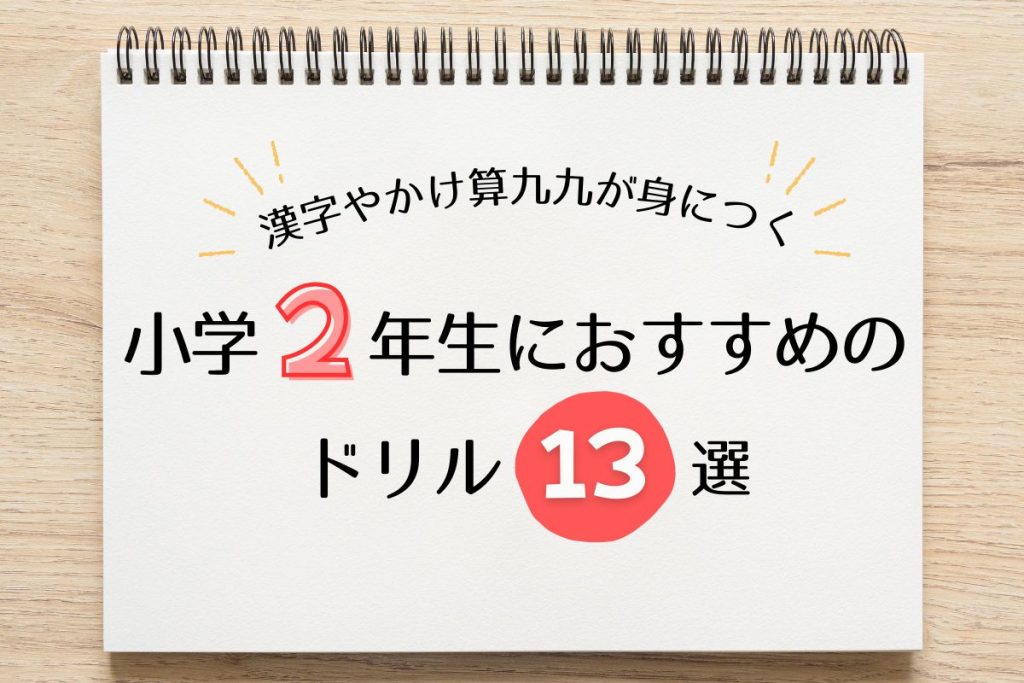


![年末年始は「ほめ」の大チャンス!叱らずに子どものやる気を引き出す方法[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/11/pixta_18285605_M_vtkM-1024x683.jpg)

![【世界が注目する日本の教育】小学校の「特別活動」について知ろう[教育評論家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/pixta_123730764_M_6mMa-1024x683.jpg)
![【小4「理科」「社会」】学びを深めるために、家庭でできることは?[教育評論家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/04/pixta_121992258_M_MOpK-1024x683.jpg)