![子どものトラブル、親は介入すべき?低学年の友だち関係「見守る」or「動く」の判断基準[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/11/pixta_70909982_M_R7JS.jpg)
「なぜか自分だけ遊びに誘われない」「消極的で大勢の輪に入れない」「言い方や容姿をからかわれる」など、低学年のうちから友だち関係で不安やストレスを抱えている子は少なくありません。「まだ低学年だから」と放置しておくと、いじめや不登校につながる可能性もあります。保護者の方が悩みを抱えたお子さんに寄り添い、豊かな人間関係に導く方法について、株式会社マモル 代表取締役CEOのくまゆうこさんにお聞きしました。
取材・文/FUTAKO企画
友だち関係のトラブル、放っておいて大丈夫?
保護者の方にまず知っておいていただきたいのは、学童期は「社会性の土台作りの時期である」ということ。幼児期までは自分中心の世界だったのが、小学校という場で集団生活を送ることによって、他者との関わりや集団のルールを学んでいく時期なのです。
それぞれが未熟なために友だちどうしの小さな衝突は出てきますが、それはごく自然なこと。ちょっとトラブルがあったからといって「うちの子は友だちとうまくつき合えないようだ」「何か問題があるんじゃないか」などと思いがちですが、むしろ「衝突があって当たり前」と、まずは見守る形がよいと思います。
ただし、「低学年で社会性を学んでいる時期だから、ただ放っておいて大丈夫」というわけではありません。何か問題があった時に、そのすべてが自然に解決するというものでもないからです。子どもが学校に通っている間ずっと親が付き添うことはできませんし、最近は小学生でもSNSやゲームを介したトラブルなどが増えてきています。お子さんの友だち関係の困りごとに気づいてサポートしたり、時には学校と共有したりすることはとても大事なことなのです。
子どものどんな様子を気にしたらいい?
「友だちの数」は気にしない
私は保護者の方向けに「親子で取り組むいじめ予防」という講演会や相談なども行っていますが、「うちの子、友だちが一人しかいないみたいです」「友だちが少ないようです」と心配されている保護者の方は少なくありません。その際、「友だちの数は気にしなくて大丈夫です」とお伝えしています。
「友だちが一人しかいない」というのは、たまたま親に話していないだけかもしれませんし、「多いからいい」ということでもありません。実際に友だちがあまりいないとしても、お子さん自身が困っていなければ、それでいいのです。保護者の方の役割は、お子さんの特性を理解して社交的なスキル向上のサポートを行うこと。過度に心配しすぎないほうがいいと思います。
「以前との変化」に注目する
気をつけたほうがいいのは、「お子さんの言動に大きな変化がないかどうか」。子どものタイプとして友だちのことをよく話す子、話さない子など違いがあるので、「以前と比べてどうか」に注目することが大切です。
「少し前はいつも話に登場していた仲よしの●●ちゃんの名前が出なくなった」「以前はよく話していたのに、友だちの話題を避けるようになった」などは、関係に変化があったサインかもしれません。
いじめというわけではなくても、クラスで「なぜか自分だけ遊びに誘われない」「消極的な性格のために友だちの輪に加われない」などと満たされない気持ちを抱えている可能性もあります。 お子さんの以前の様子と比べて変化があったかどうか、食欲がなくなったり表情が暗くなったりしていないか、などにも目を向けてみましょう。
「登校渋り」はトラブルのサイン
学校に行くのを嫌がる「登校渋り」は、トラブルの兆候と言ってもいいかもしれません。高学年だと「行きたくなくても我慢して行く」子も少なくありませんが、低学年の子ほどわかりやすく「登校渋り」に表れる傾向があります。そういう場合は「子どもだけでは解決できない何か」が起きている可能性があるので、お子さんの心に寄り添って話を聞く必要があります。
親が「正しく聞き取る」ためのヒント5

友だち関係について気になることがあった場合、説明する語彙力や表現力がまだ十分ではない年齢のお子さんに対しては特に、「保護者の方が正しく聞き取る」ことがとても大事になってきます。子どもが自分で口に出して伝えようとするだけで、解決につながる場合もあるからです。では、どのような点に注意して話を聞くとよいでしょうか。
1 「事実」ではなく「気持ち」を聞いてみる
「学校で何があった?」「どんなことがあったの?」など「実際にあったできごと」を、保護者の方から聞かれた時にすらすらと説明するのは、低学年では難しいでしょう。記憶があいまいだったり、時系列がごちゃごちゃだったりすることも多いので、保護者の方もつい「それは変だね」とか「さっき○○ って言っていたでしょう」などと横槍を入れてしまいがちです。
そうなると子どもは「きちんと伝えなければならない」というプレッシャーから、話すのが面倒になったり話したがらなくなったりしてしまいます。 そこで、話を聞く際は「今日学校でどうだった?」「どんな気持ちだった?」などと、お子さんの気持ちから聞いてみるとよいと思います。
「事実」よりも「気持ち」のほうが簡単で話しやすいことが多いものです。お子さんにとって「嫌だったかどうか」が大事なポイント。ゆっくりと話を引き出していきましょう。
2 時系列を整理して聞く
ほとんどの子どもの場合、時系列を整理して理路整然と話すのは難しいものです。1年生ぐらいだと「昨日」「おととい」の区別がまだしっかりできていなかったり、「先週の金曜日」と言われてもぴんとこなかったりもします。 順序だてて説明することが難しいためにつじつまが合わず、事実関係がおかしなことになることもありますが、保護者の方にはそれを責めたり厳密に追究しようとしたりしないで聞いていただきたいのです。
時系列がわかりにくい時は大人が手伝って、一緒に整理してあげるとよいですね。
「この前は○○ちゃんと一緒に帰ってきたよね。その時は大丈夫だったの?」などと、「実際にあったできごと」と一緒に話していくと子どもも理解しやすいと思います。そうして現実に起こったできごとを整理することで事実関係がはっきりしますし、案外子ども本人も「なんだ、そんなに気にすることではなかったな」と思える場合もあります。
3 冷静に聞く
子どもが「何か嫌な目にあった」と知ると親はつい感情的になりがちですが、できるだけ冷静に話を聞くことが大切です。子どもというのは「自分に都合のいいことだけ」言っていることもあるからです。
例えば、自分が相手に何かしたことがきっかけとなって、トラブルに発展したとしても、相手にされたことだけを言うこともあるのです。よくよく聞いてみると、「自分も相手に同じことをした」だったり、「自分がトラブルの原因だった」という場合もあります。
また、低学年だと「わざとやったわけではない」ことも多いものです。「悪気なく思いついたことを言ってしまった」「近づきすぎて手が当たってしまった」ということもよくあるので、「我が子が被害にあった!」とすぐに思い込まないほうが賢明かもしれません。 そして、子どもどうしだと、けんかをした翌日にはけろっとして仲直りということもあります。大人は「合わない人」とはすぐに距離を置いたりますが、子どもの場合はすぐに結論を求めずに、友だち関係で何かあってもしばらく様子を見守ってあげてほしいと思います。
お子さんからちょっと話を聞いただけで相手のお子さんの保護者に苦情を言ったりすることで、感情的にこじれて関係が悪くなるケースはとても多いです。学校にクレームを伝えた場合も、「そんなに大事ではなかったはずなのに大事になってしまう」場合もあります。
お子さんが「被害者側」で感情的になってしまったら、冒頭でお伝えしたように「今は人間関係を学んでいく時期。子ども同士のトラブルはあって当たり前」ということをぜひ思い出していただきたいのです。お子さんがつらい目にあっているのではないかと、もやもや、いらいらする気持ちも理解できますが、まずは冷静になりましょう。
私の相談対応の体感では、「7割くらいのケースは子ども同士で問題を解決している」という印象があります。「保護者の方が早とちりをせず、あわてて介入しないほうが結果的にうまく収まりがつく」ということは頭に入れておきましょう。
4 共感しながら聞く
お子さんの話を聞く時に気がせいて「だから、なぜそうなったの?」などと問いつめるような聞き方をすることはありませんか? 詰問されるのは大人でも嫌なものでかえって言葉が出てこなくなることもあるので、そうやって聞き出そうとするのはNGです。 まずは穏やかに耳を傾けて「それは嫌だったね」と共感しながら、お子さんの言葉を引き出してあげてほしいと思います。
子どもたちの悪口でよく聞くのは「デブ」「ブス」「服が変(ださい)」など、外見的な特徴です。言われたら大人であっても傷つくもの。そんな時はお子さんに「そんなことはないよね」「腹立つよね」「悲しいよね」と親が寄り添ってあげて、「もしまた今度言われたらママ・パパに(先生に)教えて「次に言われたら、自分で『嫌だ』って言おうね」などと声をかけるとよいでしょう。
5 話しやすいタイミングを見計らう
話を聞くタイミングも大事です。学校から帰宅してすぐに「今日はどうだった?」と聞いても、低学年だと疲れていることも多いですし、すぐ遊びに行きたい時もあるでしょう。
大人でも、仕事から帰ってすぐに夫や妻から「今日はどうだった?」などと質問を浴びせられたら「ちょっと一息つかせてほしい」と思いませんか? 子どもにも話したい時、話したくない時があって当たり前。親は聞きたい気持ちをぐっと抑えて、あせらずタイミングを見計らいましょう。
テレビを見ている時、おやつを食べている時、お風呂に入っている時など、リラックスしている時にゆっくりと話を聞けるとよいですね。
至急対処したいトラブルは?
お子さんから友だちとの話を聞いたうえで、「あわてて介入しないほうがいい」とお伝えしましたが、一方で早めに先生に共有したほうがいいこと、親がすぐに対処したほうがいいこともあります。

暴力や物を隠された時
「たたかれた」「髪を引っぱられた」「物を隠された(壊された)」
このような場合は、お子さんにできるだけくわしく聞いて、先生に共有したほうがいいでしょう。
低学年の場合は「言葉がうまく出ずに手が出てしまった」「距離が近くて、はずみで体がふれてしまった」ということもあるので確認は必要ですが、暴力に関することは早めに判断・対処する必要があります。日常的に手が出るような子だったりすると、先生は同じような事例を把握しているケースも多いものです。
また、「物を隠す」という行為は常習性があることも多いです。定期的に隠したり、壊したりするのは犯罪につながりかねません。そういった行為に及んだ相手のお子さんのためにも、先生への共有はしたほうがいいケースです。
性的なことに関する言動があった時
スカートめくりやボディタッチなどは昔からよくありますが、今や「小学生がふざけてやったことだから仕方ない」では済まされない時代になってきています。
我が子がされた場合は「こんなことがあったようです」と早めに学校に共有し、逆に我が子が誰かに対してしてしまったのであれば、きちんと注意する必要があります。
保護者の方としては「子どもってそういうことするよね」などと問題にせず流してしまいがちですが、最近は子どもの身体に対する権利意識が高まっていて、笑い事では済まされない問題になっています。
保護者の方が注意しないままでいると、子どもも「たいしたことではないんだな」と軽く考えてしまうので、「絶対やっちゃいけない。犯罪になるんだよ」と、性的なことに無神経な言動にはきちんと怒る姿勢が大切です。「たかが子どものじゃれ合い」と見過ごさないでほしいと思います。
最後に~家庭で友だちの会話を広げる

お子さんと日常的に友だちの話をしていると、お子さん自身や友だちに関して、「活発な子なんだな」「そんな発言をする子なんだな」などと、関係性が見えてくると思います。関係性がわかると、お子さんの変化にも気づきやすくなります。
「クラスにはどんな子がいるの?」などと、ふだんからよく話を聞いてみるとよいと思います。その際、お子さんの言動に対して「なんでそんなことを言ったの?」「そうじゃないでしょう?」などと、つい指摘したくなることもあるでしょう。そうなると、話したい気持ちがなくなってしまいます。
まずは共感していったん受け止めてから、もしも助言できるようなことがある場合には、「こうしたらよかったんじゃないかな」と方向を示す形であれば、素直に聞いてくれるのではないでしょうか。 親はずっと子どもの隣にはいられませんし、いちいち子どもどうしの関係性に介入してもきりがないものです。
私のところに相談に来られた方の話では「心配で寝られなかった」「腹が立って寝られなかった」などと、大人のほうが気にしすぎてしまうこともあります。
この記事を読んでいらっしゃる保護者の方なら、適切な対応を意識し、実践できることと思います。友だちとの間で多少のトラブルがあっても(親心としてはつらいところですが)、ある程度のことは子ども同士で解決できることを信じて見守っていきましょう。
この記事の監修・執筆者

一部上場企業、DeNA、ベンチャー企業にて中高生向けサービスの企画、プロモーションなどに従事。サービスを通し多くの中高生や保護者と接点を持つ中で、以前から問題意識のあった 「いじめ」を少しでもなくしたいという思いからマモルを設立。いじめ報告相談プラットフォーム「マモレポ」を開発運営するかたわら、学校コンサルティング、いじめ・ハラスメントのセミナー登壇、執筆を行う。
https://mamor.jp/parents/ 親子で取り組むいじめ防止プログラム
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪







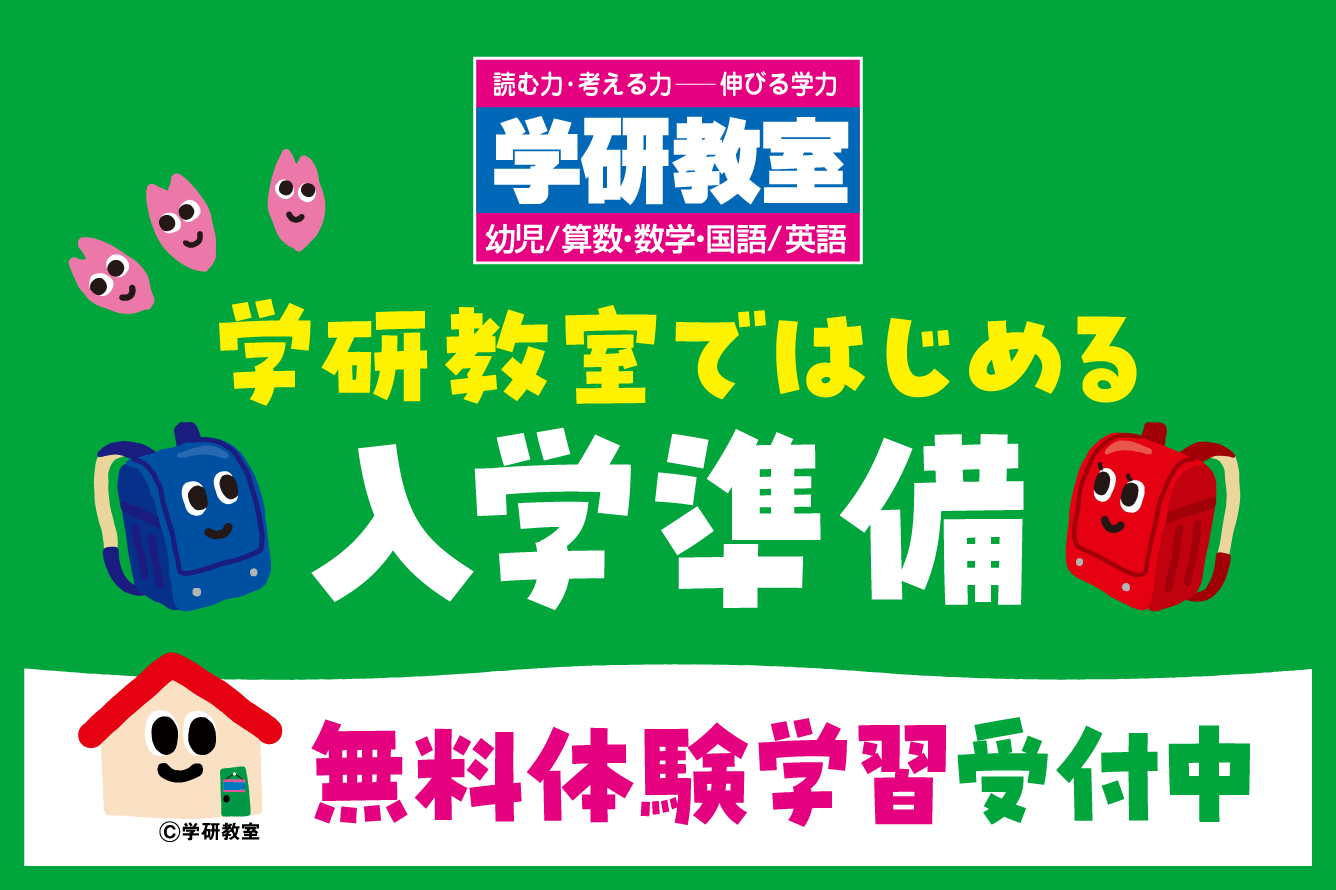















![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)





![【たたく殴る❝手が出る子❞】対人トラブルを起こしてしまう「他害」の原因・背景と、その子どもへの寄り添い方[小児科専門医監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/pixta_94426631_M_UnDh-700x467.jpg)


![【新1年生を事故・不審者から守る!】通学路の「危険な落とし穴」入学前チェックリスト[セコムIS研究所監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/pixta_80260948_M_zPZR-1024x683.jpg)


