![【ASD(自閉スペクトラム症)の子どもあるある⁉】長期休み明けの「登校しぶり」 安心して学校生活に戻れるために親ができること[小児科専門医監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/pixta_108011078_M_MRkH.jpg)
学校生活にやっと慣れたと思ったら、長期休みを挟んでまた登校をしぶるようになってしまう…など、悩みに直面しているご家庭も多い時期ではないでしょうか。
ここでは、ASD(自閉スペクトラム症)の子どもが抱えやすい困りごとや悩みについて、その原因とフォローの仕方を、発達障害の子どもについて詳しい小児科医の森博子先生に伺いました。
取材・文/細川麻衣子
ASD(自閉スペクトラム症)の子どもの特徴は?
まずは、小学生のASD(自閉スペクトラム症/以降ASD)の子どもについてです。
主に、社会性や感覚、こだわりに特性が見られる傾向があります。いっけん❝困りごと❞として表出する面が多くあるように感じられますが、実はその特性が❝才能の芽❞と捉えることができる面も多々あるのです。
【ASD(自閉スペクトラム症)の子どもの特徴】
●社会性・コミュニケーション能力・想像力に凹凸がある
「困りごと」としてあらわれる面(ネガティブな見方)⇒人との距離感をつかみにくく、相手の気持ちを読み取ることが苦手なので、場の空気や背景を気にせず思ったことをストレートに伝えてしまう傾向がある。会話で突然「誕生日は何年何月何日?」「僕の大好きな電車は〇△□でね~」と一方的に聞いたり話したりして、相手を驚かせてしまうことも。
「才能の芽」と捉えられる面(ポジティブな見方)⇒見方を変えればとても素直で率直。裏表がなく、思ったことをまっすぐに伝えてくれる。また、周りの空気に流されない分、自分の考えをしっかり持てるのも強み。ときには独特の視点で「この算数の問題はこう解くんだよ」などと、周囲をハッとさせるようなアイデアを生み出すことも。
●強いこだわりやマイルールがある
⇒予定が変わったり、いつもとは違う状況に対して大きな不安を感じるので、子どもによっては癇癪などを起してしまうことも。「シャツを着るときは必ず右袖から」「毎朝必ず同じ道順で登校する」「色鉛筆の並び順が自分の中で決まっている」などのルーティンを守ることで、安心感を保つことができる。
⇒“探究心の深さ”や“継続力”の表れ! 一度決めたことをやり抜く姿勢は、例えばクラスで多くの子どもが出来ずに諦めていることに対しても、自分の納得いくまで続けて成し遂げる! という結果につながることも多いので誰よりもストイック。そういう性格から一貫性があり、周囲から信頼されやすいという面もある。
●興味の幅・ストライクゾーンがとても狭く限定的
⇒周囲からは、興味を持てることが少なく、学校の勉強や集団活動にも消極的に見えてしまう。多くの保護者には「どうして同じことばかり繰り返すの?」「もっと他のことにも挑戦してほしいのに」と、心配をあおる行動に見えがち。また、遊びや話題が合う友だちも限られ、興味がないことには集中できず、「偏っている」と思われやすい。
⇒興味を持った分野に対しては、驚くほど深く掘り下げられるので、集中力が続きやすく、専門性を身につけやすい。他の人が気づかない細かい点まで見つけ出す“観察力”がある。将来は、研究・技術・芸術など❝一点突破❞の世界で力を発揮しやすいという絶大な強みがある。
●音・光・肌ざわりなど、独自の感覚過敏がある
⇒人によって感じ方は十色で、いっけん何でもない人混みや音、光などが、本人にとっては強い刺激でストレスを抱えてしまうことも。洋服のタグや食べ物の食感なども、ストレスになる原因。しかし周囲には「神経質」や「わがまま」と誤解されやすい。
⇒❝人一倍繊細なアンテナ❞を持っているということ。小さな違いに気づける力や、感覚を研ぎ澄ませる力は、図工や音楽など、感性を生かす教科や場面で個性を発揮しやすい一面も。

このようにASDの子どもの特性は、いっけん困りごとに見えることが多いですが、裏返せば❝才能の芽❞。今はもちろん、将来も「研究者」「職人」「専門家」としての強みにつながる要素が、こんなにも詰まっているのです!
こう捉えれば、ASDの子どもの今も将来もたくさんの希望が見えてくるはずです。
≪関連記事≫【我が子の発達に特性アリ⁉】3年生になって気づく発達障害の特徴と対応策「心がけたいことは?」[小児科専門医監修]
長期休み明けの「困りごと」は「SOSのサイン」
夏休み・冬休み・春休みをはじめ、ゴールデンウィークやシルバーウィークなどたびたび訪れる長期休みは、ASDの子どもたちにとっては楽園です♪ 一方で、慣れた場所(自宅)で自分のペースでゆっくり過ごせる長期休みから、久しぶりの学校への切り替えは大きなストレスになります。
そして実は、休み明けに突然不調になるのではなく、休み明け前の「もうすぐ学校が始まる」を感じ始めた頃から徐々にソワソワ・イライラし始めます。

そして長期休み明け――。代表的な「困りごと」として現れる主な症状は次の3点です。
●登校しぶり(「行きたくない」と登校を拒否)
●家庭での癇癪(外では出さない分、家で癇癪を起こす)
●身体的不調(頭痛・腹痛など、行きたくない気持ちが体に出る)
これらは、変化に弱く❝先❞を読むと不安になる、ASDの特性が原因です。「学校が始まる=また頑張らなきゃ!」というプレッシャーと戦っているのです。
この状態に対して、多くの保護者は途方に暮れて困ってしまうのではないでしょうか。
ここで知っていただきたいのは、この症状が出ているということは子どもにとって「SOSのサイン」だということ! 脳が環境の切り替えに追いつかず、防衛反応をしている証拠なのです。決してわがままや甘えではありません。
ASDの子どもに対する❝安心の3ステップ❞
長期休み明けに❝荒れる❞ASDの子どもに対して、どんなふうに対処していけばよいのでしょうか。保護者が心得ておくとよいポイントを3ステップにまとめてお伝えします。
【ASDの子どもに対する安心の3ステップ】
●ステップ1:安心の「見通し」をつくる
・登校までの流れを時系列で示す
・写真付きの予定表、登校ルートや教室の写真などで視覚的に伝える
・「朝一番に知っている先生に会えるようにする」など、事前に学校側と相談しておく
●ステップ2:「がんばらなくていい」ルールを先に渡す
・「今日は1時間目だけでOK」「泣いても大丈夫」「教室に入れなくてもOK」など、“できる範囲”に最初からハードルを下げておく
●ステップ3:振り返って“できたこと”に目を向ける
・「制服を着られた」「玄関まで行けた」「先生に手を振れた」など、小さな成功体験を見つける
・“自分にもできた”という実感を持たせられるよう、できることに着目する
ASDの子どもは、これから起こることを想像して見通しを立てるのが苦手なことが多く、言葉だけの説明では不安が強くなってしまうこともあります。そのため、ステップ1のように予定を❝視覚的に❞示すことが有効です。写真やイラスト付きのスケジュール、登校の流れを時系列で見える化することで、安心につながりやすくなります。
また、❝視覚支援は小さい子向け❞と思われがちですが、ASDのお子さんにとっては年齢に関係なく有効なサポートになります。小学生以上のお子さんでも❝見える形で伝える❞ことはとても効果的なのです。

長期休み明け、久々の登校初日に行きしぶったり、イライラして暴言を吐いたり……そんな子どもの様子を見て「このまま学校を休んだら、休みグセがついてしまうのでは…⁉」「私も仕事だから、学校に行ってくれないと困る!」と、焦る保護者の気持ちももちろんあるかと思います。
しかし、環境の変化に対して脳が❝切り替え❞に追いつかず、防衛反応をしている状態なので、「どうしていつもこうなの?」「早く学校行くよ!」など、焦る保護者の気持ちを子どもにぶつけてしまっては、逆効果です。
保護者は子どもに対して「安心できる材料を伝える」と共に、「ご自身の焦る気持ち⇒待つ姿勢」に切り替えることも、とても大切です。
可能であれば、保護者の方ご自身が心の余裕を保てるよう、始業式当日は登校出来ず欠席することを仮定して、前もって仕事の都合等を調整しておくことも、ひとつの方法です。
ASDの子どもの長期休み明けの実例
実際に長期休み明けが苦手なお子さんに対して、「こうしたら乗り切れた」という保護者の方の対応を含めた実例をご紹介します。
【ケース1:脳が思考停止状態で玄関でフリーズ……。(低学年/女子)】
『長期休み明けの朝、これで登校の準備バッチリ! さあ、いってらっしゃい! ……というところまできて、突然玄関でフリーズしてしまった娘。この日は、無理に学校へは登校させず欠席に。服を着られたことやランドセルを背負えたことを褒めました。この状態が2日間ほど続いたのですが、焦る気持ちをグッとこらえ、娘が自ら動けるタイミングを待ちました。すると長期休み明け3日目、自分から「いってきます」と、登校できました。』
【ケース2:始業式前日、兄弟ゲンカが勃発!(高学年/男子)】
『休み明けの少し前からイライラしている様子で、ついに学校再開の前夜に大爆発し、兄弟ゲンカに発展! でも翌日は学校へ普通に登校。でもまた帰宅すると家では大荒れ、兄弟ゲンカも勃発……。学校でも同じように荒れていないかと心配でしたが、先生に聞くと学校では普通に過ごしているとのことでした。外では頑張っていることがわかったので、「家では出していいよ」と怒らずに受け止めることにしました。数日したら「あの状態は何だったの⁉」と思うほど荒れた状態は収まり、笑顔で登校できるようになりました。』
この2組の実例で言えることは、
●初日から完璧を求めず、出来たことを褒め&静かに待ちながら見守った
●保護者自身の焦る気持ちを抑え、心に余裕を持つよう努めた
このように、子どもが家でみせた姿は安心しているからこそ出せるものです。怒らず、様子を見守ってこの状態を受け止めたお母さんたちに、拍手です!

ASDのお子さんにとって「長期休み明け」は、大きな山場です。無理やりの登校は控えて、まずは出来たことを褒める、そして見通しを与え、保護者自身が心に余裕を持って❝待つ❞こと。これらを心がけることで親子間に安心感が生まれ、少しずつ学校生活とそして❝長期休み明け❞そのものにも慣れていくことができます。
ASDの子どもの「困りごと」は、“困らせたい”のではなく、“わかってほしい”というSOSのサインです。それを受け取った保護者が、少しだけ見方を変えてくれたとき、その子の困りごとは❝才能の芽❞へと変わっていきます。長い目で、その芽を大切に育てていきましょう。
この記事の監修・執筆者

2010年熊本大学大学院医学教育部卒業。新生児集中治療室(NICU)での大学病院等勤務を経て、22年に発達診断専門の「親子のミカタオンラインクリニック」を開院。全国の親子から発達相談を受ける。自身も、注意欠陥多動性障害(ADHD)の長男と、グレーゾーンの次男を育てる。医療者であり、発達障害児を育てる当事者でもある視点から、子育てのリアルな悩みに寄り添う。
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪
あわせて読みたい
-
![【グレーゾーンと発達障害の違い】“境界知能”とは?そして子どもへの声掛けで気をつけたいこと[小児科専門医監修]](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAArwAAAHTAQMAAAD/PlkSAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAD9JREFUGBntwYEAAAAAw6D7U4/gBtUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAKiWwAB+LdYyQAAAABJRU5ErkJggg==)
【グレーゾーンと発達障害の違い】“境界知能”とは?そして子どもへの声掛けで気をつけたいこと[小児科専門医監修]
- 教育
- 小学校
-
![【字が書けない⁉】学習障害(LD)ってなんだろう[専門家監修]](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAArwAAAHDAQMAAAD86FuJAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAD5JREFUGBntwTEBAAAAwiD7p14ND2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMCjAJzLAAFxsOwYAAAAAElFTkSuQmCC)
【字が書けない⁉】学習障害(LD)ってなんだろう[専門家監修]
- 教育
- 小学校
-
![【5人に1人が“ひといちばい敏感な子”⁉】HSC(Highly Sensitive Child:ハイリー・センシティブ・チャイルド)とは?[医師監修]](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAArwAAAK8AQMAAAA3dP4AAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAFNJREFUGBntwTEBAAAAwiD7p14MH2AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADcBPNcAAHlRPJwAAAAAElFTkSuQmCC)
【5人に1人が“ひといちばい敏感な子”⁉】HSC(Highly Sensitive Child:ハイリー・センシティブ・チャイルド)とは?[医師監修]
- 子育て
- 悩み
-

【脳科学者&小児科医監修】もしかして、発達障害? と思ったら~前編<保護者はどうしたらいいの?>
- 子育て
- 悩み
-
![【入園・入学前に知っておきたい“HSC”】ひといちばい敏感な『ハイリー・センシティブ・チャイルド』の“その子らしさ”を伸ばす育て方[医師監修]](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAArwAAAHTAQMAAAD/PlkSAAAAA1BMVEUAAACnej3aAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAD9JREFUGBntwYEAAAAAw6D7U4/gBtUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAKiWwAB+LdYyQAAAABJRU5ErkJggg==)
【入園・入学前に知っておきたい“HSC”】ひといちばい敏感な『ハイリー・センシティブ・チャイルド』の“その子らしさ”を伸ばす育て方[医師監修]
- 子育て
- 悩み








![【グレーゾーンと発達障害の違い】“境界知能”とは?そして子どもへの声掛けで気をつけたいこと[小児科専門医監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/pixta_70264583_M_PdJj-700x467.jpg)
![【字が書けない⁉】学習障害(LD)ってなんだろう[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/pixta_47289812_M_yslz-700x451.jpg)
![【5人に1人が“ひといちばい敏感な子”⁉】HSC(Highly Sensitive Child:ハイリー・センシティブ・チャイルド)とは?[医師監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/09/pixta_106161567_M_56YN-700x700.jpg)

![【入園・入学前に知っておきたい“HSC”】ひといちばい敏感な『ハイリー・センシティブ・チャイルド』の“その子らしさ”を伸ばす育て方[医師監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/09/pixta_68309858_M_RFGl-700x467.jpg)












![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)

![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-700x467.jpg)







![【子どもの花粉症にどう対処する?】最新情報を知って治療&対策を考える[耳鼻咽喉科医師監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/pixta_124323214_M_j7BZ-1024x683.jpg)
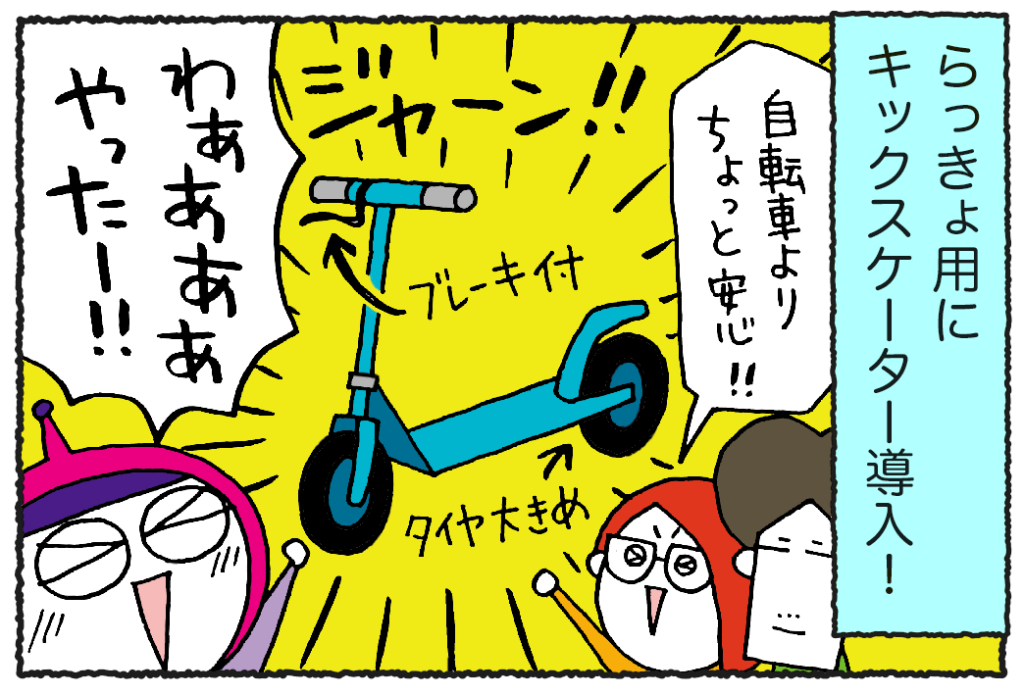
![【5・6年生になって気づく発達障害のサインって⁉】その特徴と対応策[小児科専門医監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/11/pixta_118402148_M_lX3j-1024x683.jpg)
![【たたく殴る❝手が出る子❞】対人トラブルを起こしてしまう「他害」の原因・背景と、その子どもへの寄り添い方[小児科専門医監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/pixta_94426631_M_UnDh-1024x683.jpg)
![【発達障害の子どもの進路】どんな選択肢がある?「受験」にも有効な対策とは?[小児科専門医監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/07/pixta_120686822_M_yG3B-1024x683.jpg)
![【ギフテッドって⁉】❝特異な才能を持つ子ども❞といわれる「ギフテッド」の子どもの特徴とその子どもが抱える特有の悩みとは?[小児科専門医監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/pixta_94815672_M_pUWY-1024x683.jpg)