![【学校外教育費過去最高】小学生の「習い事多すぎ」問題とは[教育ジャーナリスト監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/02/pixta_101126280_M_Y4lR.jpg)
進級・進学を機に、新しく習い事を検討しているご家庭も多いはず。選択肢が多いだけに、ついあれも、これも……と習い事の数が増えてしまったり、宿題や復習もこなさなければならず、親子ともどもへとへとになってしまったりすることもあるのではないでしょうか。
熱心な親がはまりがちな「やらせすぎ」の危険性について、教育ジャーナリストのおおたとしまささんにお聞きしました。
取材・文/FUTAKO企画
「非認知能力向上のため?」習い事の費用は過去最高額に
「子どもの教育資金に関する調査2024」(ソニー生命保険株式会社)によると、塾や習い事にかける「学校外教育費」の平均支出金額は、小学生の場合、月に1万8,914円。2014年の調査開始以来、最高額になっています。
塾や習い事にかける金額は年々高額になっています。ここ最近の物価高による影響もありますが、上記調査の「早期の知育や英才教育が子どもの将来のために重要と考える親が7割」という結果からも、学校外教育の機会を積極的に活用しようという意識が高まっていることは明らかです。
幼少期の習い事は、最近注目されている「非認知能力」の向上に影響を与えると言われています。
非認知能力とは、IQテストや学力テストでは測れない、やる気や忍耐力、協調性、自制心などのこと。習い事を通して、そうした能力を育てたいと、多くの保護者に注目されているものです。
また、少子化が進む一方で、習い事の種類は多様化し、数が増えています。
定番人気の水泳、英会話教室、学習塾、ピアノなどに加えて、野球、サッカー、バレエやダンスなど集団で行うものも人気。ここ数年はプログラミングやロボット教室、サイエンス教室、クッキングや、絵画・工作などのアート系も注目の的です。さらに、昔ながらの書道や武道(空手、剣道、柔道)、そろばんなども人気が再熱していて、どれを選べばいよいか迷ってしまうほど。
そんな魅力的な多くの選択肢を前に、入学や進級のタイミングで、新たな習い事を検討されているご家庭もあるでしょう。学年が上がるにつれて行動範囲も広くなり、これまでの習い事にプラスして複数の習い事に通われるお子さんも少なくありません。
「やらせすぎ」の4つの弊害とは
保護者のかたとしては、さまざまな習い事でお子さんに多くの能力を身につけてもらいたいと思うのは、当然のことだと思います。ただし、毎日のように習い事があるなどの、「やらせすぎ」には次のような弊害があるのです。

①スケジュールに追われ、疲れがたまる
小学生生活は、親が思うより忙しいもの。毎日の学校の授業や宿題、行事に対応するために、子どもの脳や体はフル稼働している状態です。体力がまだ十分でない低年齢の子ほど、新生活に慣れるまでに時間がかかります。 新入学や進級のタイミングで習い事の種類や頻度を増やす場合、たとえお子さん自身が「やりたい」と主張するものであっても、脳や体がついていかないこともあります。お子さんの心身に負荷がかかりすぎることがないように、大人の判断でしっかりとスケジュール管理を行いましょう。
②友だちと予定が合わなくなる
小学生になると、子どもは親よりも友だちとの関係を大事にするようになっていきます。 「放課後、忙しくて友だちと遊ぶ時間がない」「おたがいの予定が合わず遊ぶ約束ができない」というのは、子どもにとっては大問題です。
小学校低学年ぐらいだと、「この習い事を続けてほしい」という親の意志をくみ取ってがまんしてしまったり、また、言葉で伝える力も足りなかったりして、表立って親に「やりたくない」とは言わないかもしれません。 「スケジュールがぎっしりで友だちと遊べない」状態が、お子さんの気持ちや交友関係に悪影響を及ぼしていないかどうか、様子をよく観察する必要があります。
③ぼーっとする「余白の時間」がなくなる
お子さんが帰宅後、ぼーっと過ごしているとします。保護者のかたからすれば、無駄な時間に見えますし、「この時間に何かさせないともったいない」と思われることもあるでしょう。 しかし、それは大間違い。子どもには、このぼーっとする時間が大切なのです。
ぼんやり、ゆったりと脳を休める時間がないと、お子さん自身が「何をしようかな」と考える主体性や自主性を発揮する余裕がなくなってしまいます。
ぼーっとする時間を犠牲にしてまで、習い事を増やす必要はありません。
あまりスケジュールをつめこみすぎず、ぼーっとしたり自由に空想したりする時間を意識的に確保することも、お子さんにとっては必要なことなのです。
④余裕がなくなることで、親子関係が悪くなる
習い事がたくさんあって、それぞれに宿題が出たり、ピアノやバレエのように日々の練習が必要だったりすると、当然ながら子どもの生活は忙しくなります。私の感覚としては、週3回以上の習い事には注意が必要だと思います。 ご家庭の経済的な負担はもちろんですが、親の時間的な負担もまた、相当あるものと考えましょう。
たいていのお子さんの場合、自主的に習い事の宿題や練習を行うのは難しいもの。そうなると親の声がけやチェックが必要なことが増えていき、親子ともどもストレスがたまっていくことになります。
また、親としては月謝という費用をかけた分、「技術の習得」という成果を求めてしまいがちです。ですから、お子さんが熱心に習い事に通ったり課題をこなしたりしようとしない場合、つい 子どもを厳しく叱ってしまうことにもなりかねません。 こうして、習い事が原因で、親子関係が悪くなってしまう可能性もあるのです。
「必要以上にやらせすぎない」ための3つの注意点
①「親自身の不安」と折り合いをつける
「子どもにあれもこれも習い事をさせなければ」と思ってしまうのは、親自身の損得勘定から来ているように思えてなりません。
自分自身が競争社会で生きてきているために、「より能力の高い労働者でなくては」という思い込みがあり、つい他者との比較で子どもを見てしまうのです。
親である自分と同様に、お子さんも競争社会で生き抜くことを前提として、「有利に戦うための武器を身につけさせたい」「幼少期から習わせておかないと、能力が身につかない」などという、強迫観念に近い思いが、「やらせすぎ」の背景にあるのではないでしょうか。
そして、負け組になることへの恐怖、または不安から、つい熱くなってゲームに課金するように、お子さんの習い事にも「課金」してしまっているように思います。
つまり、親自身が自分の恐怖や不安を回避しようとすることが、子どもに「必要以上のものをやらせすぎる」という結果につながるのです。
しかし、習い事とは、「早期職業訓練」ではありません。将来どんなふうに生きていきたいか、そのためにどんな能力が必要かは、いずれ成長したお子さんが自分自身で考えていくこと。能力至上主義の考え方は、いったん忘れてしまいましょう。
非認知能力も、生きていくのに必要な力ではありますが、本来は生活していく中で自然と身についていくものです。
必要な非認知能力は子どもの個性によって違いますから、あれもこれもと欲ばらなくて大丈夫。「親が習い事をさせなかったら、非認知能力を獲得できない」というものではありません。 保護者のかたが、自分の感情と折り合いをつけ、親の損得勘定で子どもを振り回さないこと、「やらせすぎ」にならないようにセーブするということが、お子さんにはとても大切なのです。
②子どもの意見にも耳を傾ける
小学生になって学年が上がるにつれ、子どもも自分の意見をもつようになり、幼児期や低学年の頃のように親主導で習い事をさせることが難しくなります。親がやらせたい習い事に誘導しようとしても、うまくいかない場合もあるでしょう。
そんなときは、ぜひお子さん自身の意見にも耳を傾けてあげてください。
子どもは自分に必要なもの、好きなものを直感的に選び取るセンサーをもっています。親が無理に与えなくても、社会との接点をもってさえいれば、お子さん自身が興味を抱くことに出合って目を輝かせる瞬間は必ずあります。子どもの「好き」を見逃さないことです。
例えば、サッカーに興味をもっている子がいるとします。チームの活動で夢中になってボールを追いかけていくうちに、自然にできるようになって「選手として試合に出る」という目標に手が届くようになります。そのうちに、「こいつにはかなわない」という相手が出てきて挫折。それでも、好きだから続けてやっていくうちに、また上達していく。 このように、「夢中でやる→目標達成→挫折→好きだから克服→夢中でやる……」というサイクルを経験すること自体に意味があるのです。
ほとんどの習い事の場合、いくら技術を習得しても、それで一生食べていけるわけではありません。でも、夢中になってやっているうちに、時にくやしい思いをしながら必死に試行錯誤することに価値があります。 お子さんが純粋に興味をもって「やりたい!」と目を輝かせているときは、保護者のかたは背中を押してあげるくらいでいいのです。
お子さん自身に選択させる際に、「子どもは情報をあまりもっていないから」「まだ判断力がないから」などと、「子どもに判断させると間違える」と思われる人もいるでしょう。お子さんが選ぶ場合、結果的に適切とはいえない選択をすることもあるかもしれません。 ただし、忘れてはいけないのは、「経済合理性に照らし合わせて正しい選択をすることが、その子の人生にとって正解なわけではない」ということ。 好きなことをする喜びと出合うこと、時間を忘れて夢中になれるものに出合うことが、その子の人生を支えるようになります。
「子どもが何をすると幸せか」を第一に考えることこそ、本当に正しい選択なのです。

③習い事をスタンプラリーのようにさせない
最近は、「いろいろな習い事を経験させてみて、その中からいちばん合うものを選ぶ」という考えのご家庭もあると聞きます。とはいえ、人間が体験できる数には限界があります。 「ピアノ、水泳、集団競技でサッカーも必要。今の時代に必要だからプログラミングや、自然体験もさせよう」などと、スタンプラリーのマスを埋めていくように、さまざまな習いごとに「課金」するようなことになってはいないでしょうか。
「習い事で体験したことの中からベストなものを選ぼう」となると、結果的にものすごく限られた選択肢の中から選ぶことになりかねません。また、「体験した回数が多いから、将来の選択肢が広がる」というものではないのです。 それよりも、幼少期は実際にたくさんの大人の話を聞いたり、本を読んだりすることが、やりたいことを見つけるヒントになります。
例えば、将棋の好きなおじいさんに会って、「こういう人もいるのか、世界は広いな」と気づくだけでも刺激になります。その際、興味をもてるかどうかは関係なく、いろいろな世界との接点をもつことに意味があるのです。
これは、お金をかけなくてもできることです。
最後に~習い事は思い通りにいかなくて当然~
習い事とは本来、本人の楽しみのためにするものです。
子どもがやりたいことや相性を無視して、「ピアノは頭がよくなるから」などと、親の偏った価値観や損得勘定で決めないことが大事。習い事をいくつもさせて、親が満足しようとしないことです。 さまざまな場面でお子さんが活躍することや、技術の習得などの成果を求めすぎると、長続きしません。「思い通りにいかなくて当然」と知っておきましょう。
子どもが競争社会で生き抜くための武器を得るためではなく、好きなことを見つけて夢中になれる喜びに出合うために、習い事が存在するのです。お子さんの将来を心配するのは当然ですが、自分に自信がなさすぎる親御さんは、自分の不安を打ち消すためにあれこれやらせすぎてしまう危険があるということを、頭の片隅にでも入れておくとよいでしょう。
まずはしっかりお子さんの様子を見て、何をしているときに目が輝いているのか、何をしているときに時間を忘れるほど幸せそうなのかを把握し、お子さんの「好き」の感情を大切にしてあげてほしいと思います。
この記事の監修・執筆者

「こどもが“パパ〜!”っていつでも抱きついてくれる期間なんてほんの数年。いま、こどもと一緒にいられなかったら一生後悔する」と株式会社リクルートを脱サラ。独立後、数々の育児・教育誌のデスクや監修を務め、現在は、子育て、教育、受験、進学、家族のパートナーシップなどについて、取材・執筆・講演活動を行う。公式ブログ:http://toshimasaota.jp/index.html
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪




















![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-700x467.jpg)


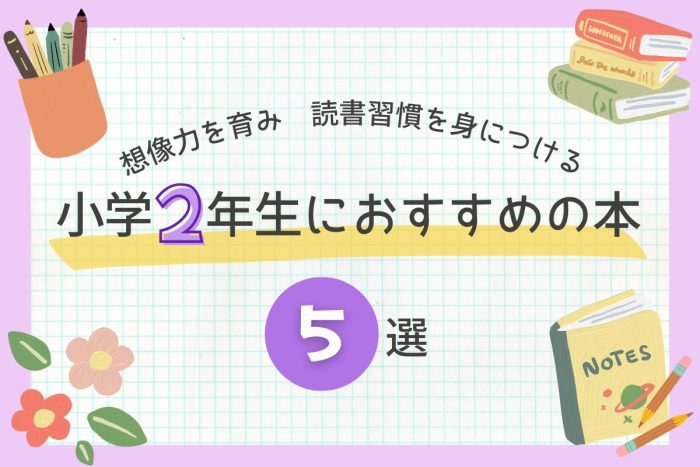



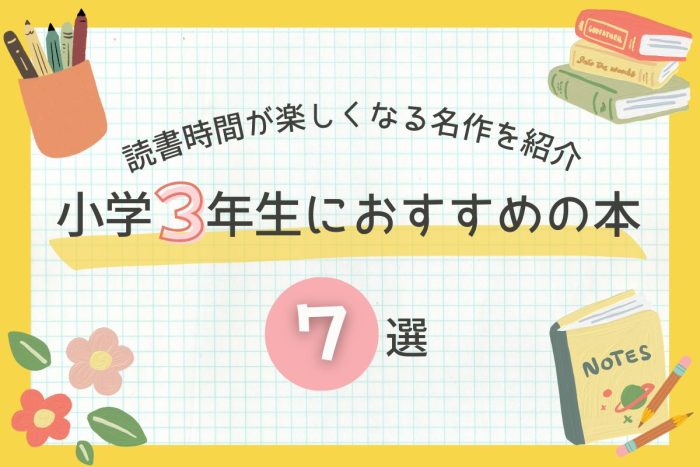
![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)





![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-1024x683.jpg)