
「五月病」ともいわれるとおり、5月は心身ともに不調が現れがちな時期。大人に限らず、春に進学・進級する子どもたちも、新たな環境や人間関係に適応するため、知らず知らずのうちにストレスをためてしまうことが多いようです。
ネット依存やゲーム依存の子どもの支援プログラムにかかわる、臨床心理士の森山沙耶さんも、ゴールデンウィーク明けに相談が増えることを指摘します。YouTubeやSNSをはじめとするネットや、オンラインゲームなどをはじめとするゲームへの依存は、子どもの学校への行きしぶりや登校拒否とも関係が深いそうです。わが子に依存があるのかどうかの判断基準や、「もしかして?」と感じたときの、保護者の対応や声かけについてお聞きしました。
文/こそだてまっぷ編集部
連休明けはネットやゲームに現実逃避しがち

お子さんによっては、新学期の緊張や疲れを引きずったままゴールデンウィークに入り、連休明けくらいから、「やる気が出ない」「朝起きられない」など、心や体の調子を崩してしまう例があります。そこから学校に行きづらくなり、結果的に家で長時間ネットやゲームをして過ごす生活になってしまうことも。新しい環境になじめないというストレスを、ネットやゲームで発散しているという面もあるということです。
子どもは依存傾向に陥りやすい

10代以下の子どもは、「理性」をつかさどる、脳の「前頭前野」が未成熟です。この前頭前野が成熟する年齢は20~25歳頃といわれており、子どもは「~したい」という欲求をコントロールすることや、リスクを予測して行動することが、大人よりも難しい傾向にあります。そのため、子どもは大人よりも早いスピードで、ネットやゲームへの依存症に進行してしまう可能性があるそうです。
「ネットやゲーム依存かも?」と思ったときのチェックリスト

お子さんにネットやゲームへの依存が疑われるとき、まずは確認しておきたいチェック項目をまとめました。お子さんの様子をよく観察し、下記の項目が複数個以上、明らかあてはまるようなら、まずは身近な相談機関 を頼ってみるのもよいかもしれません。
☑思考や行動がネットやゲーム中心になる
思考や行動において、ネットやゲームが最優先事項になってしまう。いつも頭の中にはネットやゲームのことがあり、画面から離れている時間もずっと考えてしまい、他のことが手につかなくなる。
☑現実逃避のためにやっている
イヤなことや面倒なこと、やりたくないことから逃げるためにネットやゲームをしている。画面に向かっている間はテンションが上がり、現実を忘れられる。
☑ネットやゲームに向かう時間がだんだん増えている
ネットやゲームに向かう時間が増えるほど、同じ満足感を得るためにより多くの刺激が必要になり、さらに時間や頻度を増やさなければ満足できなくなる。そしてさらに時間が増えるという悪循環に。
☑ネットやゲームができないと不機嫌になる
ネットやゲームができない状況になると、不機嫌になったり、イライラしてしまったりする。
☑ネットやゲーム以外の活動に興味を示さない
家族と行動するよりネットやゲームをする時間を優先する、現実の友達と遊びに行くよりオンラインゲームなどでの対人関係を優先するなど、リアルな人間関係に支障が出ている。また、宿題に手がつかない、成績が下がるなど、日常生活に影響が出ていてもやり続けてしまう。
☑何度もくり返し依存傾向になってしまう
一度は改善しても、何度も依存気味になる。例えば、家族の中でルールをつくり、一度はネットやゲームの時間を減らせたとしても、新たなストレスがかかるなど何かの拍子に、また元に戻ってしまう。
小学生の1日のスクリーンタイムの目安は?

2024年に子ども家庭庁が公表した「青少年のインターネット利用環境調査」によると、小学生(10歳以上)の平均のインターネット利用時間は、1日あたり約3時間46分。このうち約3時間は、趣味・娯楽に使われています。
森山さんによると、依存症の相談に来る子どもの一日あたりの利用時間は、6時間以上がひとつの目安といいます。ただし、「長時間見て(プレイして)いる」というだけでは、一概に「依存」とは言い切れないそうです。(前述の「チェックリスト」を参照)
一方で、無目的にだらだらとネットを使用することは、依存リスクを高めるともいわれています。そのため、「1日●時間」ときっちり決めることが難しければ、「終える時間」を明確にしておきましょう。一般的には、寝る1~2時間前までにデジタル機器の使用をやめることが、質のよい睡眠につながるとされています。睡眠に影響が出ると、日常生活にも支障が出てきやすくなりますし、心身の発育に影響することもあります。その点も含めて、お子さんと話し合ってみましょう。
まずは1日のスケジュールを書き出してみる
1日あたりのネットやゲームの時間の目安は、年齢や生活スタイルなどにもかかわるため、子どもの状況ごとに最適解が異なります。子どもごとの目安を知りたい場合は、いつもの1日のスケジュールを、平日・休日に分けて、円グラフなどに書き出してみましょう。宿題や勉強、習い事などの時間をふり分けると、残りの自由時間がネットやゲームの時間として使えることがわかります。
日常生活に支障を来たさない時間がどれくらいか、お子さんといっしょに考えてみましょう。
親子関係がよくなって依存が減る! かかわり方のコツ5つ

「依存はよくない」「やめさせたい」と思うあまり、つい頭ごなしにネットやゲームを批判・否定してしまう保護者のかたもいるでしょう。ただ、子どもが何かに依存気味になるのは、心が疲れていたり、ストレスを抱えていたりするサインであることもよくあります。デジタル機器を全否定して、すぐに取り上げてしまうのではなく、まずはお子さんの状況を、観察・理解することが大切です。
ここでは、お子さんが「ネットやゲームをやりすぎている」と感じた場合、自然に依存度合を減らしていくための、お子さんとのかかわり方のコツを紹介します。
かかわり方のコツ① 子どもの「夢中」を否定しない
ネットやゲームに熱中するお子さんをすぐに注意して、自分の目の前でやめさせたいというのが、多くの保護者のかたの心情ではないでしょうか。けれども、自身の感情や、「こうしてほしい」という欲求のままに、お子さんに接しないようにすることも大切です。「やめなさい」「~しなさい」という命令形で言葉かけをするのではなく、そのときお子さんが夢中になっているものに対して、まずは共感的にかかわってみましょう。
例えば、「夢中になっているところごめんね」と、子ども目線に立った言葉を添えながら、「もう夕飯の時間だけど、一度やめられる?」「寝る時間が近づいてきたけど、そろそろやめられそう?」などと促していきます。「あと2回で終わりにする」「この動画が終わったらやめる」などと、子ども自身に言わせるように促す方が、対立は避けられるはずです。
かかわり方のコツ② 子どもとかかわる時間を増やす
一日の中で、お子さんとかかわる時間を、少し増やしてみましょう。子どもはどこかで、保護者から注目されたい、ふれ合うことで安心感を得たい、と感じている部分があります。特にゴールデンウィーク明けは、新学期の緊張状態が続いていたり、がんばりすぎたりして、知らず知らずのうちに負担がかかっている時期。家族でリラックスして過ごす時間を多めにとり、お子さんがホッとできる時間を増やしましょう。
ゲームをずっとしているのであれば、いっしょにゲームをしたり、好きな映画やアニメ、YouTubeを見たりということでもOK。その中で、学校生活などで困っていることやしんどいことがないかを聞ける時間がつくれるとベターです。
かかわり方のコツ③ ルールでガチガチにしばりすぎない
保護者のかたの「こうでなければいけない」という気持ちが強すぎると、「決めたルールだから少しでも時間を超えると×」と考えることもあるかもしれません。けれども、ルールはあくまでガイドラインであり、「白か黒か」ではなく、臨機応変に対応することも大切です。
例えば、時間を少し過ぎたとしても、区切りのよいところで自分からやめられたのであれば、「キリがいいところで終わらせられたね」「ルールを意識できているね」などと、ポジティブな声かけをしてみましょう。すると、子どもも「できた」という感覚をもつことができます。そうでないと、お互いにルールが「嫌なもの」になってしまい、「決めても意味がないもの」「守りたくないもの」と認識されてしまうおそれがあります。
かかわり方のコツ④ 終了時間が視覚的にわかるようにする
スマホのスクリーンタイムや、アプリのペアレンタルコントロールなどの機能を利用して、時間を制限する方法もあります。言葉だけの注意や促しだけではなかなかやめられないお子さんには、制限機能を活用したほうがうまくいく場合もあるようです。ただ、この場合も、「いま友達とプレイ中だからもう少しやりたい」「あとちょっとでクリアできる」などの理由があれば、交渉の余地は残しておいてあげましょう。
そもそも大前提として、小学生は、自分だけで時間を管理するのは難しい年齢です。制限機能を使用しない場合は、タイマーを使用する、ホワイトボードに時間を書いておくなど、視覚的な補助も活用していきましょう。
かかわり方のコツ⑤ リアルな活動を増やしていく
結局のところ、やること・やりたいことがないから、ネットやゲームの時間が増えているケースも多いといいます。ネットやゲームは、日常の中でとても簡単に刺激が得られるツール。ほかの趣味やスポーツ、お出かけなどで、その刺激に替わる行動をつくっていくことも大切です。お子さんに今現在興味を抱く対象がなければ、以前好きだったことをまたやってみるのもよいでしょう。
また、ハマっているゲームのタイプでも、子どもの好みや特性がわかるといいます。例えば、バトル系に夢中なら対戦型のカードゲームをやってみる、育成系が好きなら実際に生き物や植物を育ててみるなど、ゲームの内容を現実に置きかえてみることもヒントになります。
もしものときの相談先は?
お子さんにネットやゲームの依存症の疑いが強いと感じられる場合は、近くの児童精神科で、ネットやゲーム依存の対応ができるところを探してみましょう。少なくともメンタルヘルスの専門医であれば、さらに適切なクリニックを紹介してくれるはずです。
はじめから医療機関はハードルが高いという場合は、まずは小学校のスクールカウンセラーや、行政の子育てに関する相談窓口に相談しましょう。そこから正規の相談窓口を紹介してもらうことも可能です。まずは保護者のかたが一人で抱えこまずに、一番身近な、相談しやすいところへアクセスしてみるとよいでしょう。
この記事の監修・執筆者

ネット・ゲーム依存予防回復支援サービスMIRA-i(ミライ)所長。一般社団法人日本デジタルウェルビーイング協会代表理事。公認心理師、臨床心理士、社会福祉士。東京学芸大学大学院修了後、家庭裁判所調査官を経て、病院・福祉施設にて勤務。2019年ネット・ゲーム依存予防回復支援サービスMIRA-i(ミライ)を立ち上げ、カウンセリングや予防啓発活動を行う。著書に『専門家が親に教える 子どものネット・ゲーム依存問題解決ガイド』(Gakken)がある。
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪







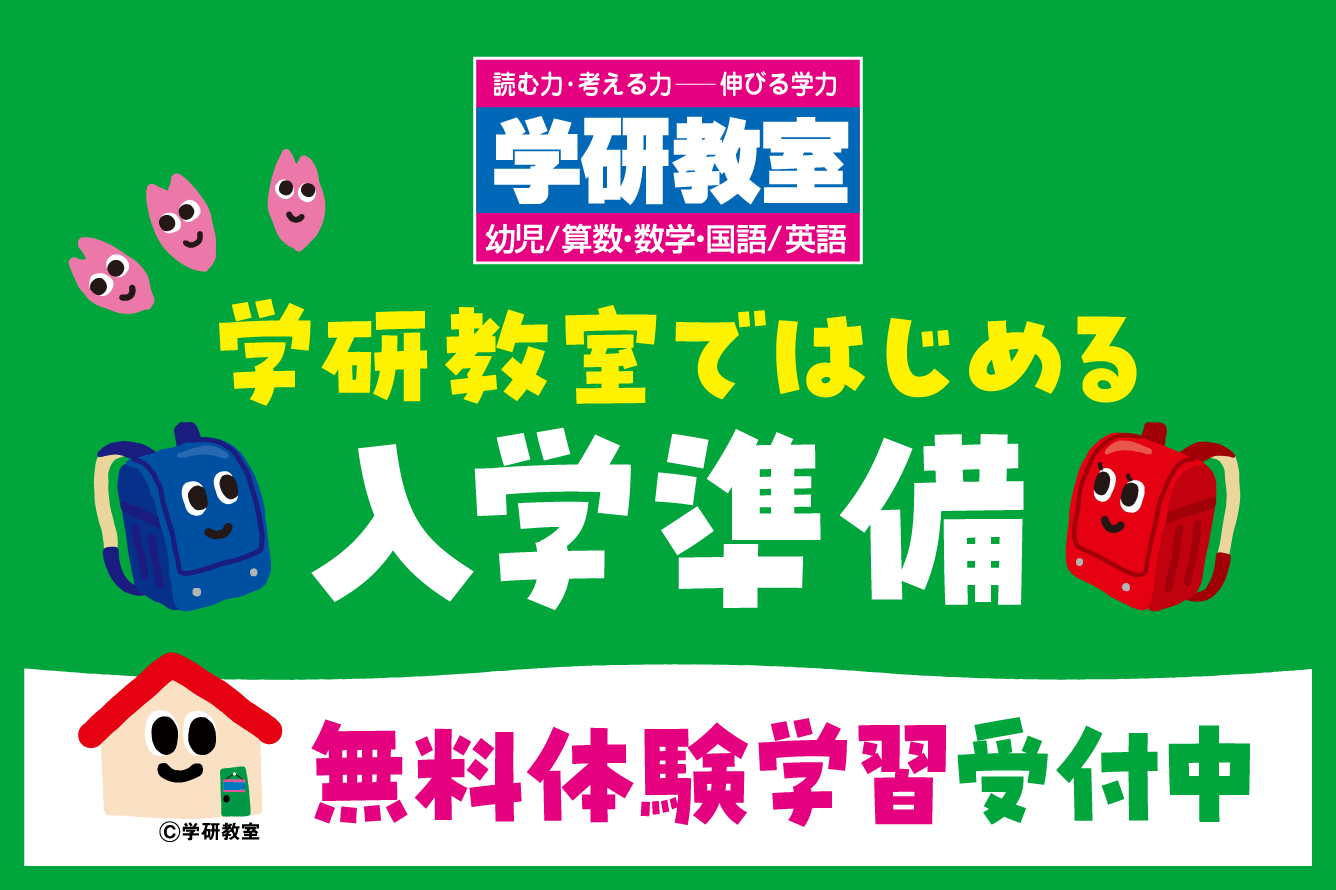


















![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)

![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-700x467.jpg)








