
子どもには「守られる」だけでなく、「意見を言う」「学ぶ」「遊ぶ」などの❝権利❞がある、という考え方が世界共通となっていることを、みなさんはご存知ですか? 1989年に国連で決められた『子どもの権利条約』が、その考え方のもととなっています。
次の学習指導要領の改訂を控える今、日本でも❝子どもの権利❞を見つめ直す動きが広がっています。
ここではそんな❝子どもの権利❞についてと、それを尊重できる家庭での親子のコミュニケーションについて紹介します。
文/細川麻衣子
❝子どもの権利❞って、どんなもの?
「子どもの権利」とは、18歳未満のすべての子どもがもっている、人間としての大切な権利のことです。1989年に国際連合総会※で採択された『子どもの権利条約』によって、世界中の子どもが守られるべき権利として定められました。日本も1994年にこの条約を批准しています。
子どもの権利は、大きく4つに分けられます。
① 生きる権利(命を守られ、健康に育つこと)
② 育つ権利(教育を受け、自分の力を伸ばすこと)
③ 守られる権利(虐待や差別、搾取などから守られること)
④ 参加する権利(意見を言い、自分に関わることに参加すること)
これらは「大人が守ってあげるもの」だけでなく、子ども自身が自分の意見をもち、社会の一員として尊重されるためのものでもあります。
例えば、学校で意見を発表したり、家庭で話し合ったり、地域社会へ参加したりするとき、「子どもも一人の人間として意見をもち、尊重される存在」だということです。「子どもだから言っても無駄」「子どもの言うことだから(無し)」ではなく、「子どもにも声を上げる権利がある」ということです。この考え方が、❝子どもの権利❞の基本です。
以前は「子どもは大人が守るもの」というイメージが強かった時代もありますが、子どもを「自分の人生を生きる主体」として見つめ直し、世界的な転換点になったものが、この『子どもの権利条約』なのです。
※国際連合総会(こくさいれんごうそうかい/United Nations General Assembly(UNGA)):世界中の国々が集まって話し合う、国際連合の中心的な会議のこと。196の国・地域が加盟している(2025年時点)。
世界の子どもを取り巻く状況と課題って?
『子どもの権利条約』採択から30年以上が経ち、世界では教育の普及や子どもの死亡率の改善など、たくさんの進歩がありました。
一方で、今の子どもたちは新しい課題にも直面しています。
例えば、地球温暖化や戦争・紛争、貧困問題などです。ある調査報告によると、気候変動による災害や戦争・紛争で、学校に通えなくなったり、家で安心して生活が出来ていなかったりする子どもは世界で数億人にものぼるといわれています。また、SNSやネットゲームの普及で、デジタルの世界でも子どもの権利が守られにくいケースが増えています。

『子どもの権利条約』に示されてはいるものの、国や地域が抱えるさまざまな課題から❝子どもの権利❞を充分に得られず難しい状況にある子どもたちが、世界には今現在もたくさんいるのです。
だからこそ、この条約を改めて知って広めていくことに、大切な意味があります。
日本の❝子どもの権利❞について
では、日本ではどうでしょうか。日本も『子どもの権利条約』を守る国として、子どもの権利を保障するための取り組みを進めています。

2022年6月に公布され、2023年4月に施行された法律「こども基本法」には、国として初めて「すべての子どもが健やかに育つ権利をもつ」と明記しました。これは、政治政策をはじめ、教育の在り方など、日本の子どもに対する考え方の土台となる法律です。
同時に2023年4月には子どもの声を社会に届けるための政府機関として「こども家庭庁」が発足しました。ここでは「子どもの意見や考えをしっかりと聞き、政治政策に反映していくこと」を大切にしています。
このように、日本では近年、子どもを大人と対等なひとりの人として尊重し、意見をきちんと聞くことを、国の取り組みとして改めて明確にし始めたのです。
教育の分野でも、次の学習指導要領の改訂(2026年度予定)に向けて、「一人ひとりを尊重する学び」や「子どもの意見を反映する教育」が検討されています。
ICTの活用や探究的な学び、多様な学習スタイルなど、子どもが❝自分の力で考える=主体性をより育む❞という教育に力を注いでいくという方針が、今現在、文部科学省からも公示されています。
けれど一方で、制度は整いつつある中ですが、実際の学校生活や家庭内では「子どもの意見が通りにくい」「遊ぶ時間が減っている」などの声も聞かれます。条約でいう「学ぶ権利」「遊ぶ権利」「休む権利」をどう保障するか――。これからの日本社会全体のテーマといえるでしょう。
家庭でできる❝子どもの権利❞を尊重する関わり方とは?
「権利」というと、言葉は少し難しく聞こえますが、日常の中でも実はたくさん関わることができます。家庭でできる小さな工夫を、いくつか紹介します。

①子どもの意見を“最後まで聞く”
日常会話の中で、つい「ダメ!」「あとでね」と言ってしまいがちですが、まずは「どうしたいの?」「そう思った理由は?」と聞いてみましょう。
自分の考えを言える経験は子どもの「参加する権利」を守り、意見を言う力を育てます。
② ❝選ぶ体験❞を増やす・繰り返す
服やおやつ、勉強の順番など、日常のあらゆる場面で選択肢を与え「どれにする?」「どうしたい?」と、子ども自身に選ばせて決定する経験をたくさんつくってください。
これによって「育つ権利」を守り、自分で決める力を伸ばします。
③ ❝失敗も大事な経験❞と伝える
失敗したときこそ、「どうすればうまくいくかな?」といっしょに考えるチャンスです。失敗を責めずに受けとめることで、「挑戦する権利」を守り、自信や粘り強さが育ちます。
④遊びや休息を削らない
勉強や習いごとも大切ですが、子どもにとって「遊ぶ」「休む」ことは、成長発達に欠かせない「育つ権利」です。
忙しい毎日の中でも、自由に遊べる時間を意識的につくりましょう。
⑤ ニュースや社会問題について気軽に話す
テレビやネットで流れてくるニュースなどの情報は、世界の子どもたちにも目を向けるきっかけになります。そこから「戦争ってなんで起こるの?」「地球温暖化ってなに?」など、家庭で話をしてみましょう。この会話が❝自分も世界の一員❞という意識を育てます。
⑥ 安心して気持ちを話せる❝居場所❞をつくる
子どもが悲しいことやつらさを感じたとき、「言っても怒られない」「ちゃんと聞いてもらえる」と思える場所は、何よりの安心の場です。親が「そんなこと言わないの!」ではなく、「そう感じたんだね」「教えてくれてありがとう」と受けとめることで、子どもは心を閉ざさずにいられます。これは「守られる権利」として、子どもが安心・安全に過ごす権利を家庭の中で支える、大切な関わり方です。
≪関連記事≫【児童手当の使い道7選】児童手当の拡充で、子どもの進路も広がる?
❝子どもの権利❞とは、子どもが「子どもである今」を、自分らしく生きるためにあるものだといえます。
そして、どんな環境にいたとしても、その子ども自身が幸せに生きるために、周りの大人がその権利を理解し、尊重することが大切です。
家庭での小さな声かけや選択の場面、安心して話せる時間などの日常の中のひとつひとつが、子どもの権利を守る行動につながっています。
「子どものために」だけでなく「子どもといっしょに」考え、ともに育ち学び合う関係をつくること。それこそが子どもの権利を生かし未来へつなげていく、私たち大人の役割なのかもしれません。
この記事の監修・執筆者

未就学から中学生までの子を持つママ編集者を中心に、子どもの学びや育ちに関する様々な情報を日々発信しています!
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪






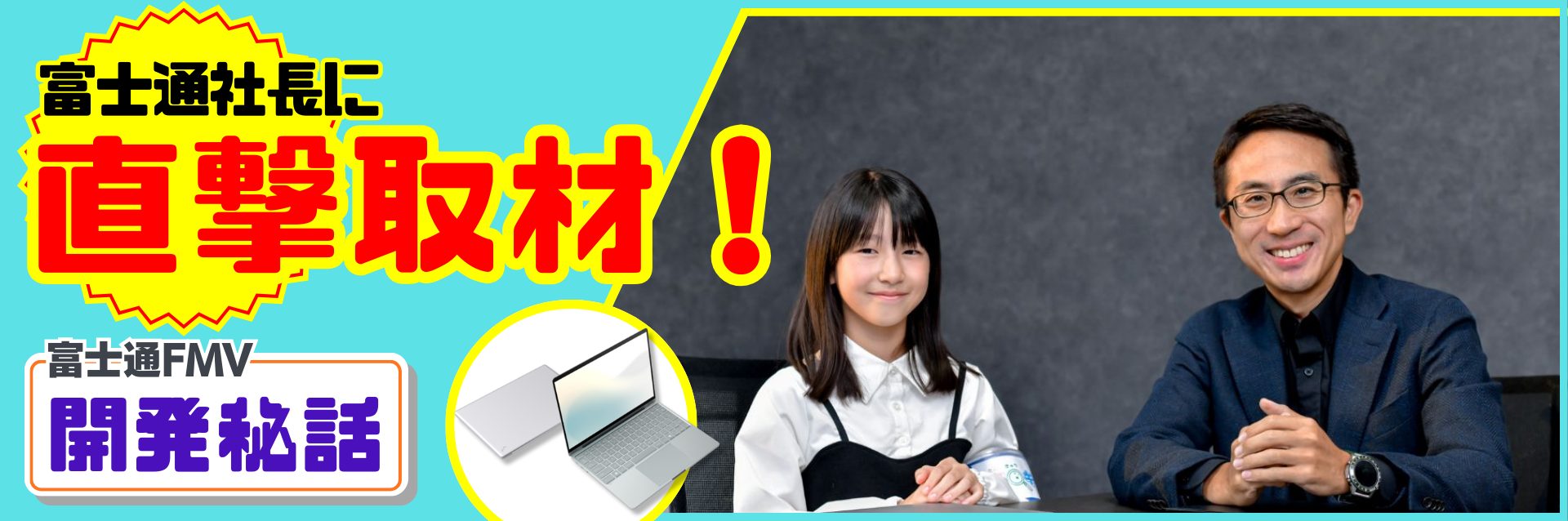






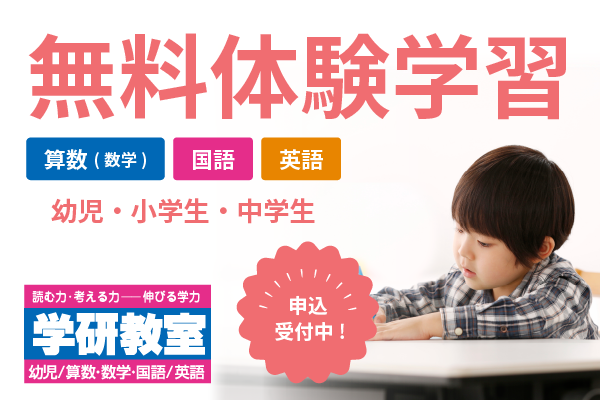














![【おせち料理を食べる理由は?】懐かしのお正月遊びにも意味がある? お正月の料理と遊びに関するQ&A[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/12/pixta_43465620_M_8vst-700x467.jpg)
![【なんで子どもは、お年玉をもらえるの?】など、お正月にまつわるナゾを解決![専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/12/pixta_58684594_M_5uhU-700x467.jpg)


![【クリスマスの雑学クイズ】親子で楽しむ★トナカイ2択クイズ[全8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_23833099_S_2MGs.jpg)






