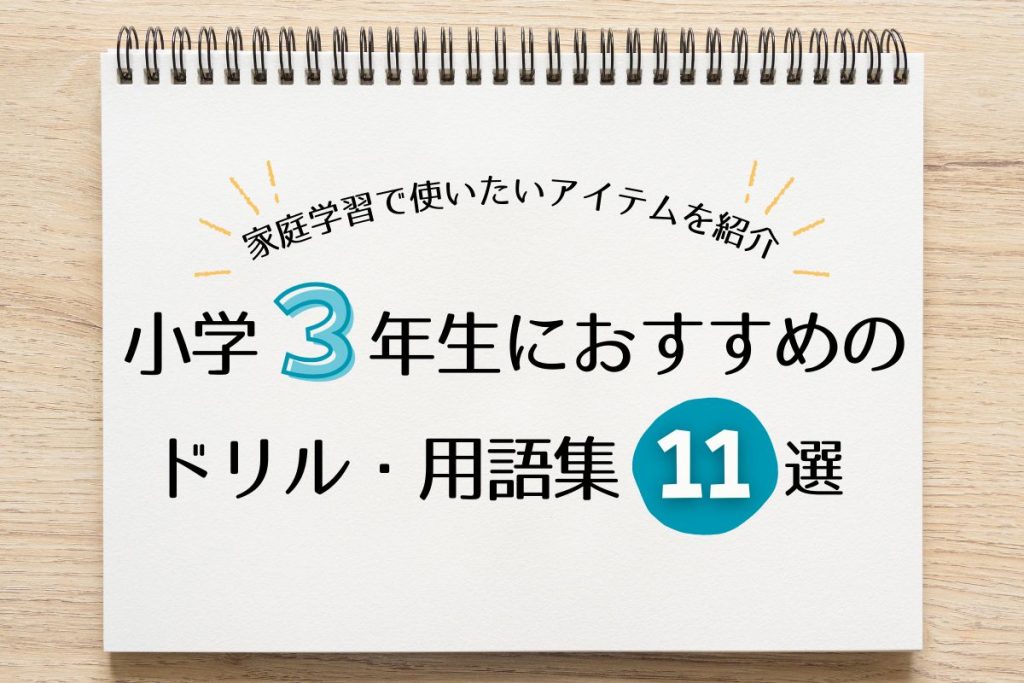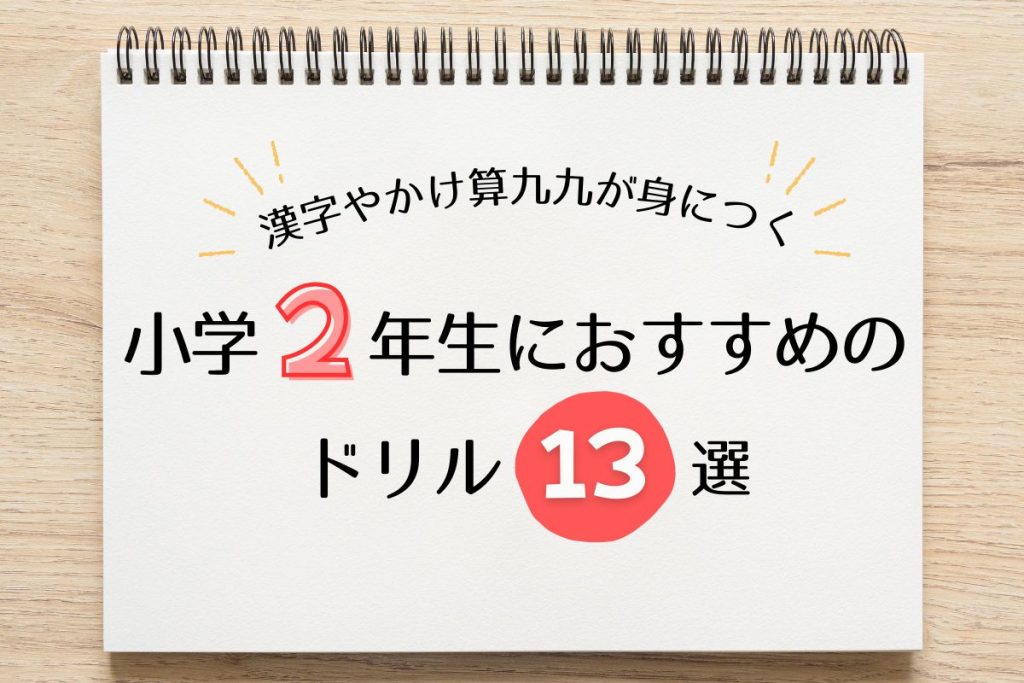3年生で学習する「漢字」は1・2年生の頃とくらべると、ぐっと難度が増してきます。ここでは難しくなってきた漢字をきれいに書けるようになるための方法・コツを、「書写」の観点から横浜国立大学 教育学部教授で書道家の青山浩之先生に伺いました。
3年生の漢字はもちろん“「きれいな字」を書く”ということについて、基本的なところから学んでみましょう。
取材・文/細川麻衣子
「きれいな字」を書くために大切なこと
「きれいな字」を書くことは、相手に読みやすい文字を書くことであり、コミュニケーション力のひとつとしてもとても重要です。また体に余計な力が入らないような姿勢をとり、力まず落ち着いた気持ちで書くことが、心地よく「きれいな字」を書けるようになる第一歩であり土台といえるでしょう。背筋を伸ばすのは、体が左右に傾き、疲労しやすい体勢になるのを防ぐためでもあります。
以下が書写の学習や文字を書くときに、大切にしたいポイントです。
① 姿勢・持ち方
② 動作・運筆
③ 筆順
④ 字形
⑤ 配列
①から⑤をひとつずつ丁寧に積み上げるように習得していくことが大切です。
①②③は自身の「書きやすさ」のため、④⑤は読む相手の「読みやすさ」のために機能することを、子ども自身も意識して学べるとよいでしょう。
保護者は書写というとつい「きれいな字を書けるようになってほしい(=④字形にこだわる)」と思うことが多いようですが、文字を整えて書けるようになるには、まず①②③の土台をしっかり身に付けることが大切です。そのうえで、④字形⑤配列(文字を並べて言葉にしていくこと)へとつながっていきます。
また、「きれいな字」を書くためには“脳内文字(頭の中に入っている文字)”の形が美しくあることが大切です。文字を書くときは、脳から信号が手に送られて文字を書きますので、そもそもその“脳内文字”が「きれいな字」であることが大事なのです。小学校や中学校で教科書などに載っているお手本の字を見て学習するのはそのためです。「きれいな字」を書くための知識を持ち、普段から自分なりの「きれいな字」を書くことで、“脳内文字”が崩れにくくなります。
≪関連記事≫【お正月の「かきぞめ」について知ろう】毛筆の学習の心得とは?〈専門家監修〉
漢字の基本点画、8つのパーツについて
漢字はおもに8つのパーツが組み合わさってできています。これを基本点画※と呼びます。「きれいな字」を書くためのステップとして、まずはこのパーツを書く動作や運筆を意識して、漢字の練習に取り組んでみましょう。前出の①~⑤の②にあたり、とても大切な基礎となります。
※基本点画:漢字を構成する最も基本となる点画のこと。「横画」「縦画」「左払い」「右払い」「折れ」「そり」「曲がり」「点」の8種類。
1年生で学習する「木」は、基本中の基本「横画」「縦画」「左払い」「右払い」が含まれます。「横画」の最後は必ず止めるようにします。これを守るだけで、丁寧な文字に見えます。長い「縦画」は、まっすぐ垂直に下ろします。「左払い」はいろいろな長さや方向がありますが、どれも徐々に筆圧を緩めながら、ゆっくり払うことが大切です。「右払い」は一度止めてから払うとしっかり書かれた文字に見えます。

次に、「折れ」「そり」「曲がり」「点」を3年生の漢字で練習してみましょう。「折れ」「そり」「曲がり」は、画の途中の形状がそのまま名称になっています。「折れ」は、一度しっかりと止めてから折ると、きちっとした文字に見えます。「そり」は緩やかな曲線に見えるように書き、「曲がり」はしっかりとカーブを描くように書きます。「点」もひとつの大切なパーツだという気持ちで、最後を止めて丁寧に書きます。


この8つのパーツの書き方を身に付ければ、他の漢字にも応用できます。
3年生の漢字を見てみよう
1年生では80字、2年生では160字の漢字を学んできました。それとくらべると、文字数自体も増え、1文字あたりの画数も増えていますので、一見「難しい……」と感じてしまうかもしれませんが、8種類の基本点画をしっかりとマスターしていれば、自信をもって書くことができます。
どの漢字にも基本点画で練習したことが応用できますので「この部分は○〇だ!」と実感しながら学びを進めてください。
【3年生で学ぶ漢字】
悪 安 暗 医 委 意 育 員 院 飲 運 泳 駅 央 横 屋 温 化 荷 界 開 階 寒 感 漢 館 岸 起 期 客 究 急 級 宮 球 去 橋 業 曲 局 銀 区 苦 具 君 係 軽 血 決 研 県 庫 湖 向 幸 港 号 根 祭 皿 仕 死 使 始 指 歯 詩 次 事 持 式 実 写 者 主 守 取 酒 受 州 拾 終 習 集 住 重 宿 所 暑 助 昭 消 商 章 勝 乗 植 申 身 神 真 深 進 世 整 昔 全 相 送 想 息 速 族 他 打 対 待 代 第 題 炭 短 談 着 注 柱 丁 帳 調 追 定 庭 笛 鉄 転 都 度 投 豆 島 湯 登 等 動 童 農 波 配 倍 箱 畑 発 反 坂 板 皮 悲 美 鼻 筆 氷 表 秒 病 品 負 部 服 福 物 平 返 勉 放 味 命 面 問 役 薬 由 油 有 遊 予 羊 洋 葉 陽 様 落 流 旅 両 緑 礼 列 練 路 和(200字)文部科学省サイトより
いかがでしたか? 「きれいな字を書く」ための基礎をしっかりと積み重ねることで、学年が上がるごとに難しくなる漢字の学習にも、応用できることがわかりましたね。書写の学習が、より豊かな学びの時間になるよう、ぜひ参考にしてみてください。
この記事の監修・執筆者

あおやま ひろゆき/書写書道の研究・教育者であり、書道家。
「美文字王子」の愛称で知られ、
テレビ番組や書籍、講演などを通じて、
美文字の普及に取り組んでいる。
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪









![【小3の国語】楽しく勉強を始めるため、春休みに家庭で取り組んでおくとよいこととは[教育評論家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/02/pixta_93546495_L_l04z-700x467.jpg)
![【小3から始まる「外国語活動」】学校の英語学習、どんなことを学ぶの? 家庭で取り組んでおくと良いこととは[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/pixta_87012342_M_k1zT-700x466.jpg)
![【小3から始まる理科・社会】理社好きの子になるために、家庭でできることは?[教育評論家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/03/pixta_78347587_M_fARs-700x467.jpg)
![【小3の算数】新学年の勉強を楽しく乗り切るため、親にできるサポート方法は?[教育評論家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/01/pixta_98402251_M_VwOw-700x467.jpg)













![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)