
小学校入学までに身につけておきたいチェックリストの「家庭生活編」。
ここでは、家庭内での生活習慣でどんなことがどこまでできていればいいか、現役小学校教諭の舟山由美子先生にうかがいます。
必要度A
早寝・早起きができる

早寝・早起きというよりも、朝すっきり目がさめるかどうかを重視してください。
たまに寝不足で朝ぼんやりしていたり、机に突っ伏してぐったりしていたりする子がいます。聞くと、夜10時ごろまで、家の人と起きているとのこと。
入学直後は特に、子どもはとても神経を張りつめて生活しています。午後8時くらいには布団に入るようにしてほしいと思います。
【一人で着替えられる?】入学までに身につけておきたいこと4つ:学校生活編
朝ごはんを決まった時間内に食べ終わる

給食は、どの学校も20分ほどで食べ終えるようなタイムスケジュールになっています。たとえ好き嫌いがなくても、食べるのがゆっくりだと、給食の時間が終わっても、お皿にまだ残っていることになり、食べ終えていないことになります。
これは私の個人的な見解ですが、食べるのに時間がかかってしまうのは、一 人っ子など、家庭ではその子のペースに合わせて食事をしている場合に多いようです。
食事は「習慣」でもあるので、好き嫌いがない、しっかりかむ、箸づかいなどのほかに、朝食を決まった時間内で食べるようにするだけで、給食も時間通りに食べられるようになると思います。
そして、夕食は家族でしっかり時間をかけて食べる、などメリハリをつけると、食事に対する感覚も育てられるのではないでしょ うか。
もう一つ、食事に関わることで大事なのは、時間を逆算して行動できるということです。例えば学校に午後8時に着くには、家をその20分前に出る必要がある。
その前にトイレに行ったり、 歯を磨いたりするとしたら、朝ごはんは、○時□分までに食べ終わっておく必要がある……ということを、画用紙などに、時計の絵とともに書いて貼って おくといいでしょう。「時計」の学習にもなり、逆算の考え方も身につきます。
朝トイレに行く習慣をつける

トイレの習慣は食事とセットです。大人でも、出るものが出ないと集中できませんよね。困るのは、授業時間にトイレに行きたくなることです。子どもはなかなか 言い出せません。
入学直後、ある子が泣いているので、「どうしたの?」と聞くと、「うんちしたい…」ということがありました。「これからは、できるだけ朝 にうんちしてこようね」と言ったら、毎朝、うんちしてきたことを報告してくれるようになりました。
もう一つの問題は、朝にうんちをしていないと給食を食べた後にしたくなることです。給食は前述の通り20分しかありませんし、その後、片付けをしたり、学 校によっては掃除の時間になったりします。ゆっくりトイレに行く時間がないので、子どもは気が気ではないのです。朝トイレに行く習慣はとても大事です。
家の鍵を開けられる

両親が共働きなどで、万が一の場合に家の鍵を開ける必要があるかもしれない場合は、自分で開けられるようにしておいたほうがいいでしょう。
必要度B
必要な持ち物をそろえられる(管理できる)
あまり多くの物があると管理しにくいので、たとえばふで箱ならば、いつも決まった数(鉛筆5本、赤鉛筆1本、消しゴム1個)が同じ場所にあるようにするとい いですね
教室では、机の中の道具箱に入れる物の配置もそろえるなどして、物を管理することを指導していきます。体操着袋なども同様です。
傘をさして安全に歩ける
傘をさして歩くのは、ほとんど学校の外でのことなので、教員も目が届きません。道路いっぱいにならないで一列で歩く、信号をしっかり見るなど、親も雨の日に一緒に通学路を歩いて確認しておくと安心です。
この記事の監修・執筆者
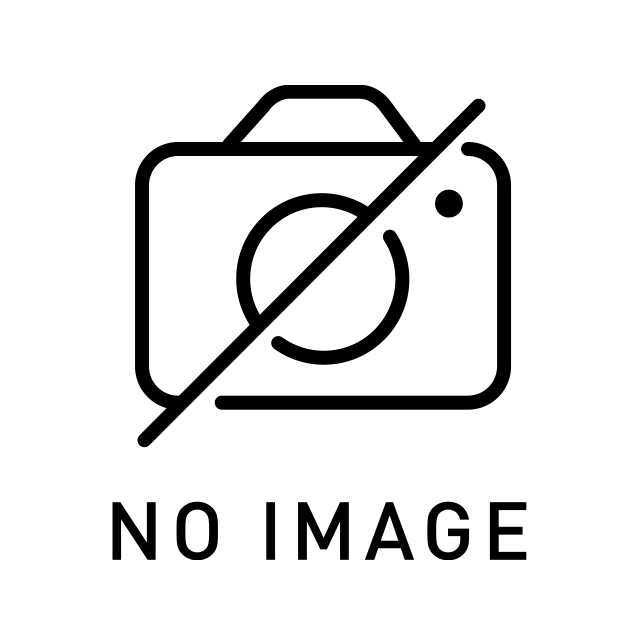
ふなやま ゆみこ/東京都の現役小学校教諭。
長年の小学生の指導経験に基づいた、
教育・子育てアドバイスに定評がある。
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪
あわせて読みたい
おすすめの本
-

頭脳開発×学研教室 入学準備 2025年度版
7大特別教材付。小学校入学までに必要な「もじ」「かず(とけい)」「せいかつ(ちえ)」を1冊で!「学研教室」とのコラボ版でたし算学習でつまずかない。1年生の簡単な漢字まで理解。はじめての「えいご」もウェブ・アプリ連動でネイティブ発音が聴ける。
-

入学準備 こくご 改訂新版
小学校入学までに必要な「こくご」の力が身につく! 「ひらがな・かたかな」の読み書き練習から、「ことば」の理解、1年生の「漢字」の入門、「音読・読解」の問題までを収録。入学前に学習することで、学ぶ楽しさを知り、机に向かう習慣付けができる。
-

入学準備 さんすう 改訂新版
小学校入学までに必要な「さんすう」の力が身につく!数と量の一致、たし算・ひき算の基礎になる「10の合成・分解」の定着、時刻の読み方「何時・何時半」の習熟、長さや量の比較など。発展でプログラミングなど、さんすうにつながる考え方を理解する。
































![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)


![【世界が注目する日本の教育】小学校の「特別活動」について知ろう[教育評論家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/pixta_123730764_M_6mMa-1024x683.jpg)


![【小4「理科」「社会」】学びを深めるために、家庭でできることは?[教育評論家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/04/pixta_121992258_M_MOpK-1024x683.jpg)



