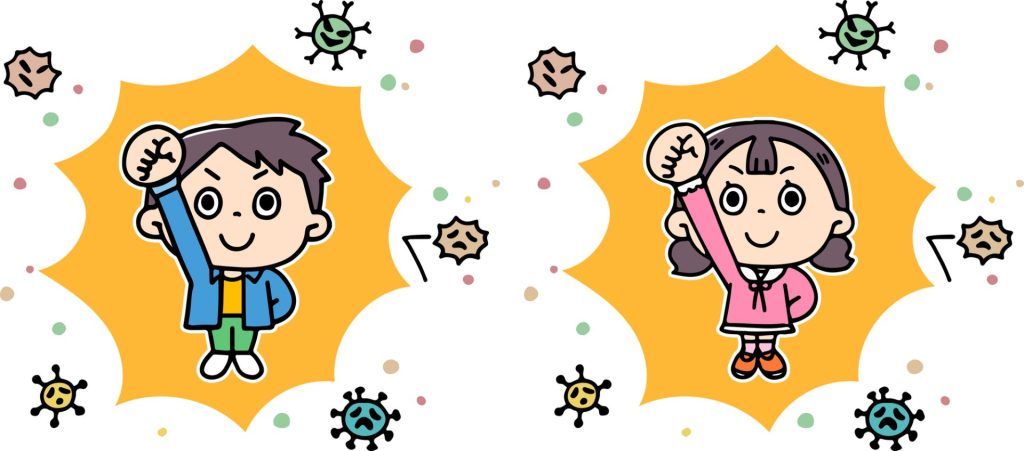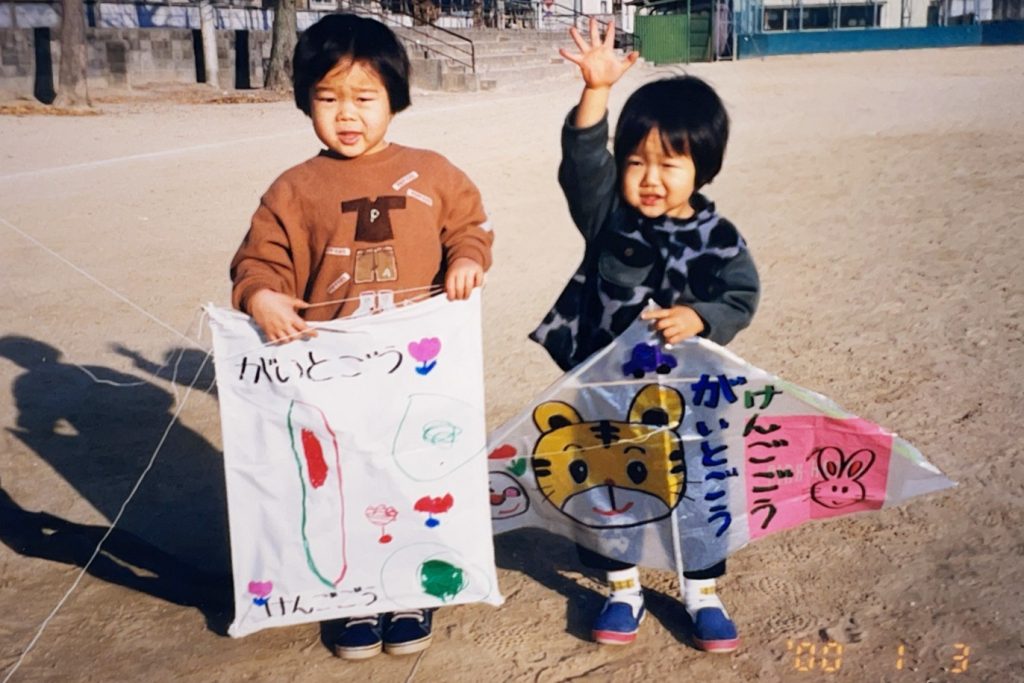まぶたが開けにくそうだったり、ものを見るときに目を細めたりと、お子さんの目の様子が気になることはありませんか?
「お子さんの目や視力について、少しでも心配になったら、気軽に小児眼科を受診してください」と話してくださったのは、小児眼科・斜視・眼瞼(がんけん:まぶたのこと)の専門医であるCS眼科クリニックの宇井牧子先生です。
今回は宇井先生に、小児眼科について、また、子どもの目の発達や症状の特徴について伺いました。
文/こそだてまっぷ編集部
小児眼科ってどんなところ?
一般的な眼科との違い
大人が受診する一般的な眼科は、目の病気の診療を主体としています。
一方で小児眼科は、まだ目のしくみが完全に発達していない、新生児から青年期までのお子さんを対象として、お子さんに特徴的な目の症状や病気だけでなく、ものを見る力の発達を支える診療を行っています。
視機能の発達を支える小児眼科
見たものを情報として理解し、適切な行動につなげるいろいろなはたらきを視機能と言い、視覚機能とも呼びます。
視機能は生まれながらに備わっているものではなく、赤ちゃんが成長し、少しずつ言葉を覚えていくように、ものを見続けることで発達します。以下のような機能を総合したものが視機能です。
[視機能]
●視力…見たものを識別する力を数値化したもの
●眼球運動…筋肉で目を動かす機能
●両眼視機能…両目で見たものを立体で認識する機能
●調節機能…見たいものにピントを合わせる機能
●視覚情報処理機能…見たことを脳で理解して処理する機能。見たものが何であるかを理解し、それにどう対応するか考え、実際に体の動きにつなげる機能
視機能が発達する時期を、視覚の感受性の期間と呼びます。視覚の感受性は生後から上昇し、1歳半をピークとして少しずつ下降し、8歳ころには終わると言われています。この大切な時期に、目の病気や弱視・斜視などの症状があると、視機能の発達に大きな差が出てくることがあります。ですので、お子さんの目の症状で心配なことがあれば、できるだけ早く小児眼科で原因を調べ、適切な治療を受けることが大切です。
小児眼科の受診の目安は?
気になる様子があれば気軽に相談
お子さんと過ごしていて、目が合わない感じがする、よくまぶしそうに目を閉じているなど、少しでも気になる様子があれば、早めに小児眼科を受診してください。お子さんが自分で目の症状を伝えるのはむずかしいものです。おうちの方の違和感を見逃さず、気軽に相談してほしいです。
[気をつけたいお子さんの様子]
●話すときに視線が合わない
●まぶたが開きにくい
●目が細かく揺れている
●おもちゃを目で追わない
●黒目が白っぽく見える
●フラッシュ撮影すると、片方の目が違う色に光って写る
●テレビやおもちゃなどに極端に近づいて見る
●目を細めてものを見る
●よくまぶしそうにしている
●上目づかいや横目づかいをする
●いつも同じ方向に顔を傾けてものを見る
3歳になったら小児眼科で目のチェックを
3歳になると、視力検査ができるようになります。自治体の3歳児健診でも視力検査が行われるのですが、小児眼科ではより精緻な目や視力の検査を行い、目の病気、弱視や近視などの有無も調べられるので安心です。最近のお子さんはスマートフォンやタブレットなどのデジタル機器に接しはじめる時期が早いので、目の健康を守るためのデジタル機器とのつきあい方についても関心をもってほしいと思います。
[デジタル画面を見るときの注意]
●姿勢を正して、画面から目を30cm以上離す
●30分に1回は目を休めて、20秒以上遠くを見る
●パチパチとまばたきをして、目が乾かないようにする
●ぐっすり眠るために、寝る1時間前からは画面を見ない
●目を休める時間を設定し、目の発育によい自然光を浴びるため、外遊びを取り入れる

≪関連記事≫【1日2時間の屋外活動で近視を予防!】子どもの視力を守る毎日の習慣、最新事情[医師監修]
気をつけたい子どもの主な目の疾患は?
眼鏡をかけても視力が十分でない「弱視」
視機能が発達する時期に、強い遠視や乱視、まぶたが開かない、先天白内障や角膜混濁などの病気があることによって発達が進まず、眼鏡をかけても視力が出ない状態を弱視と言います。
弱視と診断されても、眼球そのものに異常が認められなければ、原因となる症状を治療したり、視機能を高める訓練を行ったりすることで、視力を改善することができます。早期発見、早期治療が大切です。
ものがぼやけて見える「近視」
近くのものにピントが合って、遠くのものがぼやけて見える状態が近視です。子どもの近視の多くが、眼軸長という目の奥行きの長さが伸びすぎることで起こります。成長にともなって眼軸長が長くなると、近視の度が進行して、視力が低下します。

近視は小学校入学後から始まることが多く、遠くを見るために眼鏡などでの矯正が必要になります。思わぬ病気が隠れているかもしれないので、矯正するときには、小児眼科で診察を受け、視力低下の原因を調べることをおすすめします。
また、近視の進行を抑えるための治療も広がっています。目薬による治療や、寝るときに装着するナイトコンタクトレンズなど、治療の選択肢が増えているので、お子さんの状況に応じて取り入れることも考えてみてはいかがでしょうか。
今回は、小児眼科と子どもの目の発達や気をつけたい点について宇井牧子先生に伺いました。お子さんの目の健康と発達を守るための参考にしてください。
この記事の監修・執筆者

長崎大学医学部卒業、東京大学医学部附属病院眼科に在籍。国立成育医療研究センター眼科、横浜労災病院医長を経て、『CS眼科クリニック』院長に就任。東京大学医学部附属病院の小児眼科を担当。日本眼科学会認定眼科専門医。
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪










![【小1の4人に1人が裸眼視力1.0未満!?】視覚障害のリスクも!? 低年齢で進む子どもの近視の実態とは[医師監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/02/pixta_74205094_M_ooQt-700x467.jpg)















![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)






![【子どもの花粉症にどう対処する?】最新情報を知って治療&対策を考える[耳鼻咽喉科医師監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/pixta_124323214_M_j7BZ-1024x683.jpg)