【親子で楽しみながら観察力をアップ!】身近な場所で気軽にバードウォッチングを始めよう!

お子さんと野鳥を探して、その姿をよく観察してみませんか? 秋冬はバードウォッチングを始めるのにぴったりの季節。10月の第2土曜日(2025年は10月11日)は国連が定める「世界渡り鳥の日」でもあります。お子さんが、生物や身近な自然に興味を持ち、観察力を育むよい機会になるでしょう。今回は、気軽に始められるバードウォッチングについてご紹介します!
お子さんとバードウォッチングを始めるなら秋冬がおすすめ!
冬を越す野鳥が近くにやってくる
バードウォッチングは一年中できますが、秋から冬にかけては、冬を越すためにシベリアなど北の地域からやってくる野鳥や、高山から平地に移動する野鳥が多いため、たくさんの種類の野鳥を、街や公園など身近な場所でも見ることができます。
葉が落ちる
木々が葉を落とすので、枝に止まる野鳥が見つけやすくなります。また、視界が広くなった水辺では、カモの仲間などをじっくり観察できます。上着や手袋など、防寒対策をしっかりして観察しましょう。
秋冬に見られる身近な野鳥[10選]
秋冬には、一年中日本に生息しているスズメやハクセキレイなどの「留鳥」たちや、日本の中で季節的な移動をする「漂鳥」、冬を越すためにシベリアなど北の地域からやってくる「冬鳥」が見られます。まずは、身近な野鳥から観察して、見分けられる種類を増やしていきましょう。
1.スズメ

全長14~15cm 留鳥
見られる場所:街や公園
日本中で見られる身近な鳥で、茶色の頭と黒いほおが特徴です。体をきれいにするために、砂浴びや水浴びをする姿も見られます。冬を越すために、秋からたくさんエサを食べて脂肪を備えるので、ふっくらと丸い体型になります。寒さが厳しくなると、羽を立てて空気の層をつくり、寒さをしのぐ姿を「ふくらスズメ」と呼びます。
2.キジバト


全長約33cm 留鳥
見られる場所:街や公園
背中はうろこのような模様で、首に黒色と青色のしま模様があります。以前は街には冬になるとやってきましたが、通年見られるようになりました。公園や神社などで群れているドバトとは異なります。ドバトは人が飼っていた外来鳥が野生化しました。キジバトとドバトが同じ場所にいることもあります。ドバトにはあるくちばしの付け根の白いこぶが、キジバトにはありません。模様や鳴き声も異なるので、鳥を見分ける練習をしてみましょう。
3.ハクセキレイ

全長約21cm 留鳥
見られる場所:水辺、街や公園
横長の体で尾が長いセキレイの仲間です。海岸や河川の水辺から、街の道路や駐車場までよく見られる鳥で、地面に降りると長い尾を大きく振り、素早く歩く姿も特徴的です。背中の羽は夏は黒く、冬は灰色になりますが、顔と腹は白いままです。
4.シジュウカラ

全長13~14cm 留鳥
見られる場所:街や公園
街や公園、山林など、さまざまな環境で暮らしています。頭が黒く、ほほが白く、胸の部分に黒くネクタイのような模様があります。「ツツピーツツピー」と鳴く声が特徴で、人が用意した巣箱にすみついたり、エサ台に来たりする身近な鳥の一種です。
5.モズ

全長約20cm 留鳥
見られる場所:街や公園
春から夏にかけて山地で繁殖し、秋になると平地に降りて越冬します。秋に「キィーキィキィ」と声高く鳴いてなわばりを確保することから、秋を告げる鳥とも言われます。体はそれほど大きくないものの、くちばしはタカのようなカギ型で、小鳥を捕らえることもあります。とがった小枝や有刺鉄線などにバッタやカエルといった獲物を串刺しにする習性があり、「モズのはやにえ」と呼ばれます。
6.ヤマガラ

全長12~14cm 留鳥
見られる場所:森や林
赤茶色の体で、「ニーニー」と特徴のある声で鳴きます。森や林で一年中見ることができる鳥ですが、秋冬に葉が落ちると見つけやすくなります。落葉樹の多い公園などで探してみましょう。足で木の実を押さえて、つついて食べる習性があります。
7.ルリビタキ


全長約14cm 漂鳥
見られる場所:森や林
高山の森林で繁殖し、冬になると低い場所に降りてくるので、公園などでも見ることができます。オスは青い体で、メスは尾がわずかに青く、日本で見られる青い鳥として人気があります。オスもメスも群れはつくらず、1羽ずつで生活しています。
8.オシドリ

全長40~50cm 漂鳥
見られる場所:池や湖
カモの仲間のなかでも、ひときわ目立つ美しい色彩のオスと、地味な色のメスがつがいでいることが多いです。仲のよい夫婦を表す「おしどり夫婦」の言葉のもとになっている鳥ですが、実は冬ごとに新しいつがいを形成します。オスの羽色は秋ごろから色鮮やかに変わります。
9.キンクロハジロ


全長40~50cm 冬鳥
見られる場所:池や湖
オスの目が金色、体が黒色、翼に現れる帯が白色で、キンクロハジロと名付けられました。メスは全体的に濃い茶色です。主に冬になると日本にやってきますが、ごく一部が夏にも残っています。水の中に潜って、貝や小エビなどのエサをとります。
10.ユリカモメ

全長35~45cm 冬鳥
見られる場所:海岸や河川
冬になると日本各地の海岸や河川などの水辺にやってきます。カモメの仲間のなかでは小型で、赤いくちばしと足が目立ちます。冬は白い頭が、春先に日本を去るころには黒い頭巾を被ったようになります。東京都の鳥に指定されています。
≪関連記事≫【小4「理科」「社会」】学びを深めるために、家庭でできることは?[教育評論家監修]
観察のルールとポイント
バードウォッチングのルール
野鳥には近づきすぎず、大声を出さずに静かに観察します。必ず大人と出かけ、野鳥にエサをあげたり、触ったりするのはやめましょう。日の出から日の入りの2時間前くらいまで活動する野鳥が多いので、午前中や日中の時間帯で行うとよいですね。公園や寺社など身近な場所から始めて、野鳥を見ることに慣れてきたら、山や川、海など、さまざまな場所へ出かけましょう。
おすすめの道具
双眼鏡があると、大きくはっきりと野鳥の姿が見られます。初心者にも使いやすい8〜10倍のものを用意しましょう。双眼鏡では絶対に太陽を見てはいけません。見つけた野鳥の名前や特徴を調べるために、持ち運べる野鳥図鑑や、スマートフォンのバードウォッチング用のアプリケーションを準備しておくと便利です。撮った写真や録音した鳴き声をアップロードすることで、野鳥の種類を識別できるアプリケーションもあります。
観察のポイント
野鳥を観察したら、メモを残しましょう。見つけた日時と場所、野鳥の名前、や色や模様、飛び方や歩き方、鳴き声など、気づいたことを記録します。あとでまとめれば、自分だけの野鳥図鑑ができますね。バードウォッチングを楽しむことで、調べる力や観察力、まとめる力を身につけることができるでしょう。
今回は、秋冬に親子で楽しんでほしいバードウォッチングを紹介しました。まずは身近な場所を散歩して、野鳥を探すところから始めてみませんか?
この記事の監修・執筆者

未就学から中学生までの子を持つママ編集者を中心に、子どもの学びや育ちに関する様々な情報を日々発信しています!
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪











![[七五三]の由来、なぜ? どうして? にお答えします【専門家監修】](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/10/pixta_60574372_M_Crry-700x466.jpg)


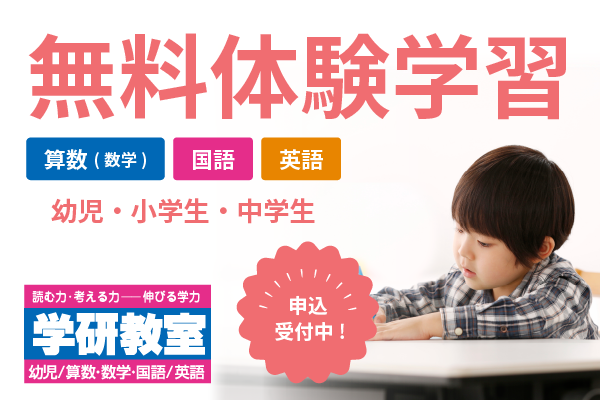










![【おせち料理を食べる理由は?】懐かしのお正月遊びにも意味がある? お正月の料理と遊びに関するQ&A[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/12/pixta_43465620_M_8vst-700x467.jpg)







![【クリスマスの雑学クイズ】親子で楽しむ★トナカイ2択クイズ[全8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_23833099_S_2MGs.jpg)


![【本が好きになる“ビブリオバトル”とは?】小学生も楽しめてコミュニケーション力もアップ![専門家インタビュー]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/pixta_75479306_S_xlCz.jpg)



