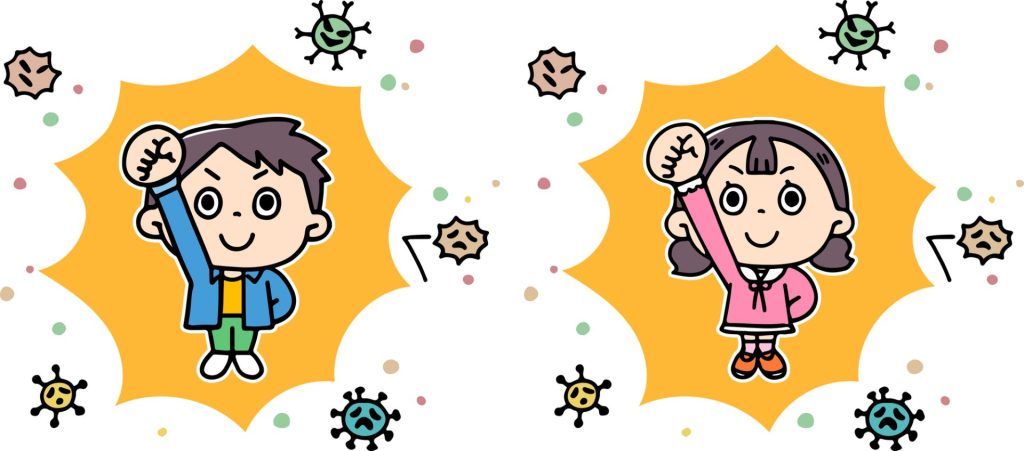![【「勉強しなさい」は逆効果⁉】「ポイ活」でやる気を引き出す「子ども手帳」のススメ[教育評論家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/04/pixta_94025360_M_gFyT.jpg)
「宿題やったの?」「ピアノの練習は?」「部屋を片づけなさい!」。子どもに毎日同じような声かけをくり返している保護者のかたは多いのではないでしょうか。それでも子どもは生返事で、なかなか動こうとしない……。そんな状況もよくあるはずです。
実は、子どもを動かすのは「言葉」ではなく「仕組み」。教育評論家の石田勝紀さんが提案するのは、「子ども手帳」という仕組みです。具体的には、お子さんのやることをTo Doリストとして見える化し、やったことに「ポイント」を与えることで、やる気をアップさせるというもの。用意するものは、100均などでも買える手帳1冊。仕組みをしっかり整えることで、子どもたちにやる気が芽生え、自主性が育つといいます。
文/こそだてまっぷ編集部
子どもへの声かけが聞いてもらえないのはなぜ?

前提として知っておきたいのは、「ほとんどの子どもは、親の声かけでは動かない」ということ。その理由は、「言葉」には「感情」がのっているからです。例えば、「ありがとう」「ごめんね」などの言葉も、状況や言い方によっては、受け手を嫌な気持ちにさせることがあるはずです。
多くの場合、親が子どもに「〇〇させよう」とする意図をもってかける言葉の裏には、「イライラ」という感情が乗っているのです。そしてお子さんにより強く伝わるのは、親に言われた言葉よりも、「イライラ」の感情のほう。そのため、声かけは結局、逆効果にしかならないことが多いのです。
ゲームは自分から始めるのに、宿題をしないのはなぜ?

宿題は言われないと手をつけないのに、ゲームは言われなくても自分から始める……。そんなお子さんも多いのではないでしょうか。多くのお子さんは、ゲームが大好きで、その理由は「楽しいから」です。では、なぜ楽しいのかというと、「できた」という感覚を得られるからではないでしょうか。ゲームの中では、レベルが上がったり、アイテムが手に入ったりすることで、「成長の見える化」が行われます。自分の成長が「見える」ことで、ドーパミンが出てやる気が上がり、ハマるような「仕組み」がつくられているのです。
もちろん、毎日の宿題や勉強、生活習慣も、すべてが成長につながっているのですが、子どもにとってはその成長は見えにくいもの。そのため、なかなかやる気を出すことができないのです。
子どもに「時間の概念」が育つのは意外と遅い

また、子ども自身が意図的に宿題をしていないわけでもないことも、覚えておきましょう。子どもは、大人がもつような時間の概念が未発達です。つまり、「未来」や「過去」という時間軸がうまく意識できず、「今」に全集中しがちです。
大人は「未来」や「過去」の概念をもっているので、過去の失敗から学び、未来のために準備します。反対に、子どもが同じ失敗をくり返しがちなのは、時間の概念が未発達だから。そして、時間の概念がはっきりと身につくのは、個人差や男女差はあるものの、早くて小学5年生くらいになってからです。それまでは、「今」やりたいこと・楽しいことしかやらない、という傾向が強く出てしまいます。
「子ども手帳」でTo Doを見える化!

これまで述べてきたような実情からすると、実は保護者のかたの「声かけ」以上に効率がよいのは、子どもが自分で動きたくなる「仕組み」づくりだということがわかるのではないでしょうか。
今回ご紹介するのは、教育評論家の石田さんが、自身の子育てや、多くの子どもたちを指導してきた経験を踏まえて考案した「子ども手帳」。1冊の手帳を使って、子どものやる気を引き出すという「仕組み」です。手帳には、子どもが「やること」を一週間単位でリストアップします。そして、できた項目にはポイントが付き、そのポイントがお小遣いなどのごほうびに変わる、という仕組みです。

「やること」とポイントの数を、週の頭に書き込みます。

できたらシールを貼る仕組み。壁に貼ればいつでも目に入ります。
子ども手帳のメリット① 「今日やること」が把握できる
大人が頭に入っているような日常のルーティンも、時間の概念が未発達の子どもには、明確に認識できていないことが多々。そこで、手帳に「今日やること」をリストアップし、一覧できるようにすることで、宿題・勉強や生活習慣のTo Doが、自然と把握できるようになります。
子ども手帳のメリット② 「ポイント制」でやる気が引き出される
多くのお子さんは、やればやるほどポイントが増えるので、うれしくなってモチベーションが高まり、手帳を続けられるといいます。心理としては、大人もハマりがちな「ポイ活」のようなものです。
子ども手帳のメリット③ 勉強が自然と「習慣化」する
子ども手帳に書き込みながら楽しく続けているうちに、手帳に書いた「やること」が習慣化してきて、努力しなくても毎日できるようになっていきます。やがて子どものやる気の源も、「ポイント」ではなく、「できる自分がうれしい」という内発的動機づけにスイッチしていくはず。そうなれば、もう「ポイ活」は卒業です。手帳がなくても、自分の力でできる子どもになっていくのです。
子ども手帳のつくり方
それでは、具体的に手帳のつくり方を紹介していきましょう。
※出典:『勉強しない子には「1冊の手帳」をあげよう! パワーアップ完全版』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)より
STEP1 子どもの同意をとり、手帳を準備する

最初は、「1週間のやることを手帳に書いて、やり終わったらポイントが貯まる楽しい方法があるよ。どう? やってみる?」などと誘ってみましょう。ただし、そこで「やってみる!」ではなく、「やりたくない」と言われた場合は、潔く引き下がるのが正解。けれども、数週間~数か月後に時期を見計らって、再度誘ってみるのはアリです。子どもの状況や気持ちはどんどん変わるので、「今は時期ではない」と考えましょう。
「やってみる」と言われた場合は、子どもが気に入る手帳を準備しましょう。基本的にどんな手帳でもよいのですが、オススメは、見開きで1週間が一覧できる、縦軸のウィークリータイプのもの。エクセルで自作したり、カレンダーに書き込んだりするご家庭もあるようです。
実は「紙質」も重要なポイント。無意識的にさわりたくなる、めくりたくなる紙の手帳を選びましょう。子どもは特に、触覚に敏感です。お子さんといっしょに店頭に行き、実際にさわったりめくったりしてみて、お気に入りの手帳を選んでみましょう。
STEP2 スケジュールは1週間だけ決める

まずは「1週間だけ」など、期限を決めて始めてみましょう。お子さんがハマりそうなら更新制にして、続けていきます。手帳を始めてみても、子どもが今ひとつ乗り気でなければ、無理して更新する必要はありません。ただし、前述したように、あとで時期を見計らって、再度誘ってみるのはアリです。
STEP3 タスクの書き込みとポイント設定

宿題や勉強、生活習慣について、毎日のタスクを、お子さんと話しながら決めていきます。いつやるのか、完了したときのポイントをそれぞれ何点にするのかも決めます。
大切なのは、「やるべきこと」だけではなく、「やりたいこと」もリストに入れること。「やるべきこと」(=イヤなこと)しか書かれていないリストは、あまり見たくなくなってしまいます。例えば、「ゲームをする」「アニメを見る」などもあえてリストに組み込み、ポイントが付くようにします。ただし、「やるべきこと」はポイントのレートを高く、「やりたいこと」は低く設定しましょう。つまり、「宿題をする」が10ポイントなら、「ゲームをする」は1ポイントなど、もらえるポイント数には差がつくようにしましょう。
STEP4 終わったタスクは赤ペンで消す

書き込んだタスクが終わったら、赤ペンで横棒を引いて消します。
なお、やれなかったことは消しません。消せなかった分は、目に見える形で残るため、お子さま自身も「やらないと……」という気持ちになっていくはずです。
STEP5 毎週末、消したタスクをポイントに清算する

毎週末に、たまったポイントを清算します。ポイントの還元先は、お小遣いだけでなく、ゲーム・動画視聴の時間延長などでもいいでしょう。1ポイントが1円か5円かなど、換金レートも子どもごとにちがってOK。親子で話し合ってルールを決めましょう。
ポイントをお小遣い化する仕組みには賛否あるかもしれませんが、自分の力で獲得したお金(ポイント)だからこそ、より大切にお金を使うようになったという例もあるようです。
「子ども手帳」を続けるポイント5つ

いざ「子ども手帳」を始めてみたいと思ったものの、「うちの子は続けられるかな?」と不安に思う保護者のかたもいらっしゃることでしょう。そこで、続けていくために、事前に知っておきたいことを紹介します。
①手帳は、「子どもがいつも見える場所」に置く
「子ども手帳」は、閉じてしまっておくものではありません。中面が見える状態に開いて、毎日見る場所に置いておくことが大切です。いつも見える状態にしておけば、忘れずに取り組むことができるからです。
②親は「できていないこと」に口を出さない
お子さんができなかった項目に対して、保護者のかたが「できていないよ」「もっとがんばろう」などと口を出すのはNG。できなかった項目は、ポイントが入らないだけ。本人もわかっているはずなので、お子さんの自主性を尊重する意味でも、口を出さないようにしましょう。
ただし、できた項目については、「すごいね」「がんばっているね」など、積極的に言葉をかけてあげましょう。
③「ポイントを細分化」してみる
例えば、ひとくくりで「宿題」という項目をつくると、なかなか手をつけられないお子さんもいます。その場合は、「ランドセルから宿題を出したら1ポイント」「問題を1問解いたら1ポイント」「1ページ終えたら5ポイント」などと、細分化していくのも手。そうすれば、途中までできることも増えるはずです。
そもそも子どもたちが宿題をやらないのは、最初の第一歩が面倒くさいから。反対に、一歩さえ踏み出せれば、あとは進めていける可能性も高いのです。
④「ポイントアップキャンペーン」を取り入れる
「ポイントアップキャンペーン」と銘打って、1週間限定でポイントを倍にするなど、遊び心をどんどん取り入れてみましょう。わざと「ポイント1.5倍」などと、半端な数字に設定するのも◎。お小遣いがかかっていれば、子どもも一生懸命に計算し、計算力も高まるかもしれません。
⑤必ずしもポイント制でなくてもよい
ポイントはある意味、行動させるためのモチベーション。けれども、「私はポイントがもらえるからやるわけじゃない」と言うお子さんもいるでしょう。その場合は、ポイント制にこだわる必要はありません。お子さんによっては、「手帳にやるべきことを書き出して消し込み作業をする」だけでもOKです。
1冊の手帳で親子のコミュニケーションが変わる
多くの保護者の方がお子さんに望むのは、日々のTo Doを義務的にこなすことではなく、自ら主体的に行動できるようになることではないでしょうか。「子ども手帳」は、うまく使いこなせれば、子どもたちの成長と変化をサポートしてくれる頼もしい存在となるはずです。
そして、保護者のかたの日々の声かけも、イライラしながらの「やりなさい!」から、子どもを認める「すごいね!」に変わっていくはず。親子のコミュニケーションが変わり、子どもの自己肯定感を上げるきっかけにもなりそうです。
この記事の監修・執筆者

音声配信Voicy
https://voicy.jp/channel/1270
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪









![【その子育てはサービス過剰?】子どもの主体性を取り戻す「3つの問いかけ」とは[工藤勇一先生監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/11/pixta_68310294_M_2s2R-700x467.jpg)















![【すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり!】素材のおいしさを引き出す「シンプル蒸し」レシピ3品[りよ子]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/canvaaikyacchi-1_ZhYH-700x466.jpg)








![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-1024x683.jpg)