
「家庭の教育方針ってどう考えたらいいのか…」と悩んだり、「うちの教育方針が間違っていないか心配…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
子どもの成長において、家庭の教育方針は非常に重要です。
この記事では家庭の教育方針を決める際のポイントをお伝えします。この機会に、子どもの成長をしっかりとサポートできる環境づくりについて考えてみましょう。
文/ハイドジア
おうちでの教育方針ってどれくらい大切?

おうちでの教育方針は、子どもの成長に大きな影響を与えます。特に小学生の時期は、人格形成や学習習慣が根付く大切な時期なので重要です。
ここからは、
- 教育方針が子どもの成長に与える影響
- 教育方針がもたらすメリット
を解説します。
家庭の教育方針が子どもの成長に与える影響
教育方針とは、どのように子どもを育てるかの指針です。たとえば、勉強に対する姿勢や人間関係の築き方など、おうちでの教育方針が子どもの価値観や行動に大きく影響します。
教育方針は、子どもが自分自身を理解し、社会での役割を果たすための基盤となるのです。
教育方針はママパパの考えを具体化すること
おうちでの教育方針は、子どもの成長にとって非常に重要です。家族全員が同じ目標を持つことで、子どもは迷わずに安心して成長できる環境が整います。
習いごとを始める際に、ママとパパが異なる意見を持っていると「どちらを信じればいいのか…」と子どもが混乱することがあります。しかし、家庭内で方針を一致させることで、子どもは自信を持って活動に取り組むことができるでしょう。
また、ママとパパのコミュニケーションが深まり、家庭内の雰囲気も良くなるかもしれません。
さらに、子どもを叱るときはルールも徹底させることが大切です。ママパパがその時々の気分で対応を変えると、子どもは親を信頼しにくくなります。一貫性のある態度で接することで、子どもは安心感を持ち、自己肯定感も高まるでしょう。親が感情的にならず、冷静に子どもに向き合うことで、子どもは健全に成長することができます。
家庭の教育方針を決める3つのポイント

教育方針を決める際には、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 理想の将来像を考える
- 親の行動指針を考える
- ルールを決めておく
1.理想の将来像を考える
子どもが将来どのような人間に育ってほしいか、親として願う子どもの理想の将来像を考えます。
たとえば、「自分で考え、判断し行動できる自立した人になってほしい」「自分も他人も大切にできる人に育ってほしい」などです。
理想の状態がわかれば、それらを実現するために、おうちではどのような関わり方をすればいいのか、どのような習慣をつくればいいのかなどを考えることができます。
2.親の行動指針を考える
理想の将来像を描けたら、それを実現するために親の行動指針を考えます。家族や親として、どのような関わりができるのかを書き出してみてください。
先ほどの「自分で考え、判断し行動できる自立した人になってほしい」を教育方針にしたとしましょう。それを実現できるための親の関わり方として、「子どもから質問されたときは、すぐに答えを教えず、まずは子どもに考えてもらう」とか「夏休みには、お手伝いを1日ひとつ子どもにさせる」など、具体的な行動レベルに書き出すことで、日々の生活で親は教育方針を意識した関わりができるようになります。
3.ルールを決めておく
教育方針とは、言わば親の大切な価値観を子どもに伝えていく基準やルールとなるものです。日々の子育てでは、その大切な教育方針から大きくかけ離れた子どもの言動が見られることもあるでしょう。
たとえば、「自分も他人も大切にできる人に育ってほしい」といった教育方針を掲げているのに、子どもがお友だちを叩いてしまうといった状況です。
子どもの言動に対して「言葉で言い合うのはOKだけど、暴力はNG」など、許容できることと許容できないことの基準を決めておくことで、ルールを守らない言動に対しては叱ることができます。
子どもを尊重した教育方針にする3つのコツ

親の大切な価値観を伝える教育方針を決めることは大事なことですが、一方的な押しつけにならない配慮も必要です。そのために大事なコツを紹介します。
1.親の意見に偏らない
教育方針は親だけで決めるのはおすすめしません。親の意見だけでなく、子どもの意見や感情も尊重することが大切です。
「体力をつけてほしい」という教育方針のもと、スポーツが嫌いな子どもを無理矢理にスポーツクラブに入れるよりも、読書が好きな子どもには図書館に徒歩で通う頻度を増やすことで、体力をつけることもできます。
子どもが興味を持つことや得意なことを見つけ、それを伸ばす方向で教育方針を考えると良いでしょう。
さらに、おうちでの意見交換を積極的に行い、異なる視点を取り入れることで、より豊かな教育方針を築くことができます。このように、親の意見に偏らない教育方針を目指すことで、子どもが多様な価値観を持ち、柔軟な思考を育むことが可能となります。
2.おうちでの方針の一致を図る
ママとパパの意見が合わない場合、一番困るのは子どもです。
「どちらの言うことを聞けばいいのだろうか」と戸惑うことになります。方針の一致を図るためには、まずママとパパの間でのコミュニケーションが欠かせません。お互いの考えをしっかりと共有し、共通の目標を設定することが大切です。
また、定期的に話し合いの場を設け、必要に応じて方針を見直すことも効果的です。
3.学校教育とのバランスも考える
また、学校教育とのバランスも考えて教育方針を決めるようにしましょう。学校では学問や社会性を育む場としての役割がありますが、おうちではそれに加えて子どもの個性や夢を尊重する環境を整えることが求められます。
たとえば、「学校で学ぶ内容が多すぎて、おうちでの時間が足りないかもしれない…」と感じる子どももいるかもしれません。
このような場合、おうちでの学びを学校のカリキュラムとどのように調和させるかを考えることが大切です。子どもの興味を引くような家庭学習の時間を設けたり、学校の宿題とおうちでの学びのバランスを取る工夫をするのもいいかもしれません。
また、学校の先生とコミュニケーションを取り、子どもの学習状況を把握することも有効です。これにより、学校と家庭の両方で子どもが充実した学びの時間を過ごせるようになります。バランスを取ることで、子どもがストレスなく学べる環境を整えることができるでしょう。
おうちの教育方針を考えるために

小学生の子どもにとって、教育方針は未来を左右する大切な指針です。今一度家庭の教育方針を見直してみてはいかがでしょうか。ぜひ、この機会にまずはママとパパで話し合ってみてくださいね。
この記事の監修・執筆者

幼稚園教諭を経て、現在は保育・教育分野を中心にアンガーマネジメント研修を行うほか、保護者向け講演会、子ども向け授業でもアンガーマネジメントを教えている。
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪


















![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-700x467.jpg)


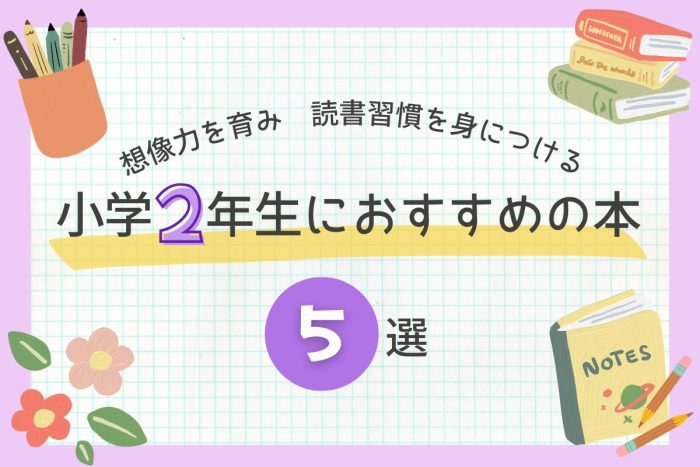


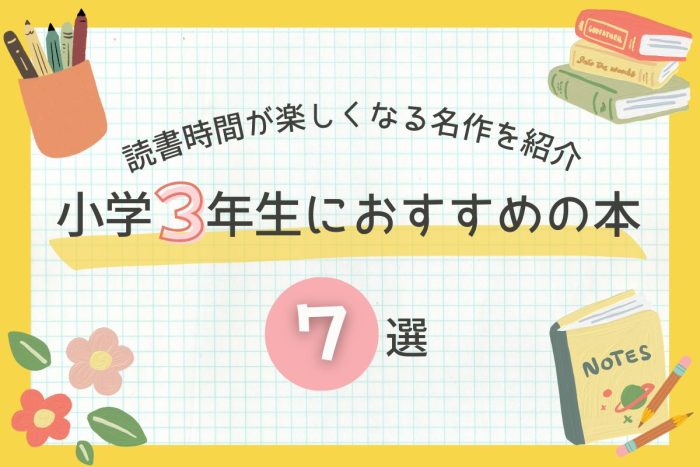
![【読めたらすごい!】河馬? 海狸? この動物の名前なーんだ?[難読漢字クイズ*8問]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/6-2title_tFXO-612x700.jpg)




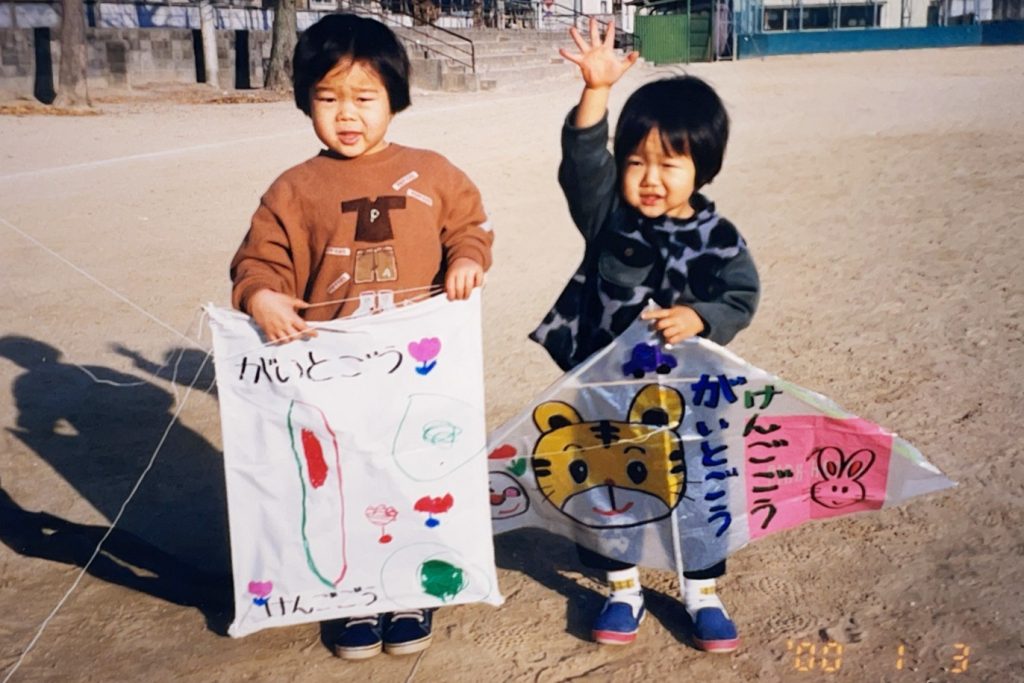

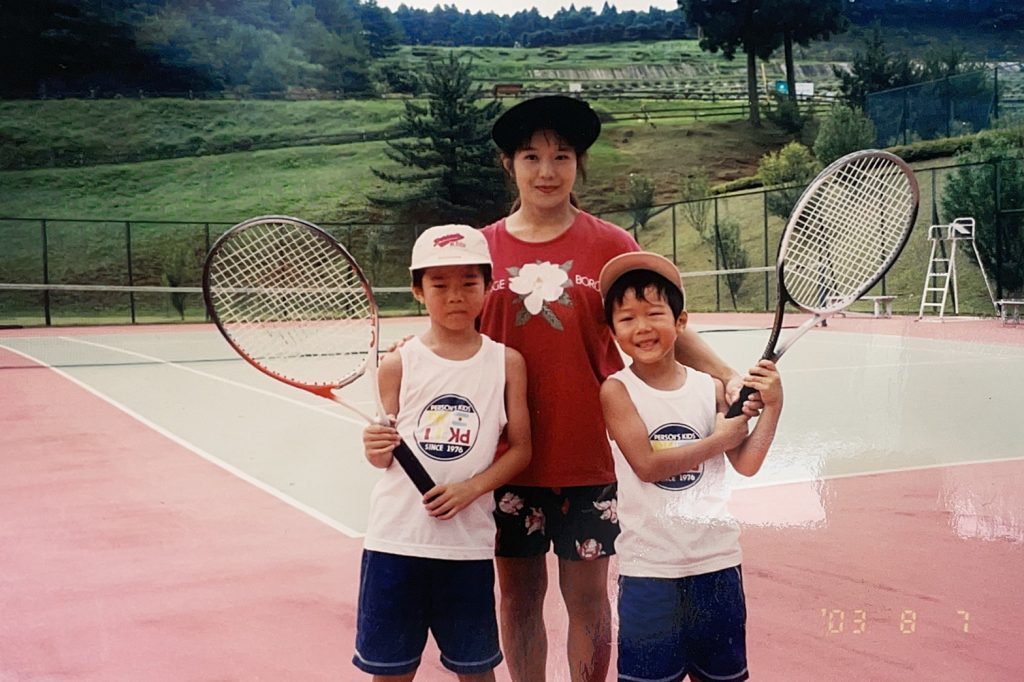

![【キレやすい子どもにならないために】怒りをコントロールする、子どものアンガーマネジメントとは[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/03/pixta_68994405_M_stTO-1024x1024.jpg)
![【子どもに怒鳴ってしまうあなたへ】「後悔しない怒り方」のための、アンガーマネジメントとは?[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/03/pixta_7687230_M_nmEb-1024x896.jpg)