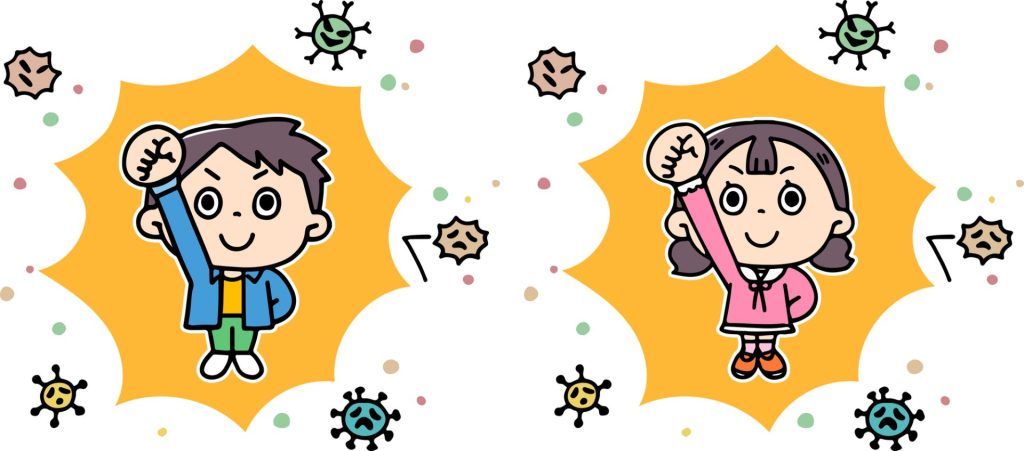![【身長は遺伝が8割、はまちがい?】「成長限界」を作らない生活習慣とは[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/pixta_86841839_M_DB94.jpg)
子どもの身長がどれだけ伸びるかについて「遺伝による影響が大きい」と考える人は少なくありません。「親の背が高い子どもは高身長、親の背が低い子どもは低身長」というようにお考えの保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、身長は決して遺伝だけで決まるものではありません。保護者の方が適切な生活習慣について知り、サポートすることで、仮に保護者の方の身長が低かった場合でも、お子さんの背が伸びる可能性は高まります。
子どもの身長を伸ばすのに必要な生活習慣について、血液栄養アドバイザーの佐藤智春さんにお話を伺いました。
取材・文/FUTAKO企画
身長が伸びるメカニズム
「身長は遺伝」とよく言われますが、私は、どれだけ身長が伸びるかについては遺伝よりも生活習慣による影響が大きいと考えています。これまで「栄養コンサルタント」として詳細な血液データから健康状態を把握し、多くの人に健康指導を行ってきた経験から、「身長の伸び」と「生活習慣」は密接にかかわっていると言うことができます。
「背が伸びる」というのは、「骨が伸びる」ことです。
身長は骨の両端にある「骨端線(成長線)」が細胞分裂して骨が長くなることで伸びます。骨端線は生まれたての赤ちゃんが最も多く、思春期の終わり頃になると閉じてしまいます。そうなると、身長はほぼ伸びなくなります。
この骨端線を伸ばすためには、成長ホルモンの存在が欠かせません。そこで、成長ホルモンの材料となるタンパク質や必要な栄養素を毎日の食事で摂ることが、子どもの身長を伸ばすための重要なミッションになります。
また、成長ホルモンは深い睡眠によって大量に分泌され、睡眠が浅いと分泌されにくくなります。そのため、質のよい睡眠をとることも大切です。
さらに、身長が伸びる時期にはタイムリミットがあります。成長ホルモンが大量に分泌される時期はある程度決まっていて、男子なら13歳から18歳、女子なら10歳から13歳がピーク。この時期にぐんと身長が伸び、その後3~4㎝程度しか伸びないことが多いです。特に女子は初潮を迎えて性ホルモンの分泌が盛んになると、身長が伸びづらくなります。
女の子だと小学3年生ごろから、男の子は中学生ごろから成長ホルモンのピークの時期が始まります。ですから、この時期に「何を食べて何を食べないか」「どう過ごすか」といった生活習慣が子どもの体に大きく影響するのです。
身長を伸ばすために大事な4つの生活習慣
お子さんの身長をできるだけ伸ばしたいと願う保護者の方は多いと思います。では、どんな生活習慣に変えていけば身長が伸びるのでしょうか。身長を伸ばすための生活習慣として大事なのは、①食事、②睡眠、③運動、④心の健康です。これら4つのポイントについて、それぞれ説明していきましょう。
① 食事~何を食べ、何を食べないか

まずは、毎日の食事が鍵となります。骨の成長を促すためにも、バランスのとれた食事や規則正しい生活を意識することが大事です。身長を伸ばすためには「体に成長を促すホルモン」と、「骨を伸ばすために必要な栄養素」の両方が揃っていなければなりません。
意外と摂れていない!タンパク質~肉・魚・卵など
身長を伸ばすために大事な栄養素として、第一に挙げられるのがタンパク質です。タンパク質は成長ホルモンの材料となり、骨の成分にとって一番大事なものです。 成長期は大人よりもたくさんのタンパク質をとらなければならないので、体重1kgあたり1.5gのタンパク質を毎日とることを意識しましょう(体重30kg→タンパク質45g程度)。
こうお伝えすると、「お肉ならたくさん食べているので大丈夫」と思われるかもしれません。しかし、実際は意外と必要な量が食べられていないことが多いのです。
人間の体はおおよそ60%が水分ですが、動物性の肉も同様に60%が水分、20%がタンパク質です。それが、加熱調理することでタンパク質の量は100gにつき8~10g程度に減ってしまいます。1日200gの肉を食べても約20g、1割のタンパク質しかとれていない計算になるわけです。これは、魚についても同様です。
魚も肉と並んで、動物性タンパク質を含む優秀な食材です。魚にしか含まれない脳の成長によい栄養素・オメガ3系と呼ばれる脂質があり、肉と比べると消化がよいので、学力向上のためにも肉と魚をバランスよく食べるとよいでしょう。
加えて、卵は成長期に必要な栄養素がたくさん含まれる、とても優秀な食材です。1個あたり6~7gのタンパク質がとれるので、成長に合わせて、成長期は1日2~3個くらい食べてもかまいません。
骨を丈夫にするカルシウム~小魚・乳製品など
骨を伸ばすタンパク質に対し、骨を丈夫にするのがカルシウムです。
「成長期には大人よりもたくさんタンパク質を摂取するのがよい」と先にお伝えしましたが、タンパク質は骨のベース、それにカルシウムで石灰化が起こり、骨が強くなります。タンパク質と共に、カルシウムも比例してたくさんとるメニューがおすすめです。摂取の目安として、タンパク質50gに対して、カルシウムは1000mg。意識してメニューに取り入れましょう。
煮干しやししゃも、わかさぎ、いわしなどの魚は、骨までまるごと食べられるのでおすすめです。
牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品はカルシウムの吸収率が高く、毎日の食事に取り入れやすい食材です。ただし、牛乳は大量に摂取することで鉄分不足を起こし、貧血状態となることがあるため、飲みすぎには注意。
他には小松菜や水菜、厚揚げなども積極的にとるとよいでしょう。
また、カルシウムはビタミンDとマグネシウムを一緒にとると吸収率が高くなるので、あわせて食べるのが大事です。
日本人の98%が足りていないと言われるビタミンDは、不足するとO脚になりやすいです。日光の紫外線を浴びることによって体内で生成されますが、食事からとるほうが効率的です。鮭、いわし、さんま、うなぎ、卵黄がビタミンDの豊富な食材です。
さらに、マグネシウムはカルシウムと一緒に働くので、意識してとりたい栄養素です。1日の中でマグネシウムとカルシウムは1対2の比率が理想です。豆(枝豆)、ごま、わかめ(海藻)、野菜、魚、しいたけなどにマグネシウムが含まれています。「ま・ご・わ・や・さ・しい」と覚えましょう。
おやつを甘いものでとらない
ここからは、身長を伸ばすことを邪魔するため「食べすぎ注意」の食品・栄養素をお伝えします。それは糖質やスナック菓子、ウインナー、インスタント食品など添加物の多い食品です。おやつや間食にすることも多いと思いますが、糖質の多い嗜好品は尿にカルシウムが排泄されたり、また、ビタミンB群が代謝に使われて、良い栄養素も排泄されたりします。肥満や生活習慣病、落ち着きのない行動にもつながります。
【おやつ・間食にNGなもの】
・糖質たっぷりのお菓子や菓子パン、スイーツなど
・砂糖を多く含んだ炭酸飲料やジュース
・添加物の多い加工食品、インスタント食品
基本的には、砂糖を多く使ったものをお子さんの間食にするのは控えたほうがいいと思います。食事の前に甘いお菓子を食べると、血糖値が急に上がって満腹になり、食事の際に必要な栄養素がとれなくなります。
また、糖質のとりすぎはインスリンを過剰に分泌してしまい、低血糖症状になると脳疲労を起こしやすくなります。食べてすぐ眠くなる子であれば、身長を伸ばすホルモンの働きを悪くしてしまいます。
さらに、添加物の入った食品を多く摂取することで、体の中で亜鉛不足を起こすことがあります。食品添加物が、亜鉛の吸収を妨げるためです。亜鉛は、DNAの細胞分裂に必要な栄養素のため、身長が伸びるときのコピー栄養素として大切です。
せっかく食事に気をつかっていても、間食でリスクのあるものを摂取してしまうと、思うように体に栄養素が届かないことになります。
そこで、間食に選ぶなら、下記のようなカルシウムやタンパク質、ビタミンを含むものを選ぶとよいでしょう。
【おやつ・間食にOKなもの】
・ゆでた枝豆
・牛乳
・パルメザンチーズ
・ゆで卵
・しらすやごまのおにぎり
・スライスれんこんに乾燥桜えびのピザ
・焼きいも・干しいも
・果物 など
②十分な睡眠
小学生に必要な睡眠時間は9~10時間とされています。 そのためには、眠る1~2時間前には入浴を終える必要があります。これは、寝る直前に入浴すると体温が上がり、寝つきが悪くなるためです。入浴したあと体温が下がってくる頃にベッドに入ると、スムーズに入眠できます。
また、少なくとも1時間前にはスマホやゲームを使わないことも大切。目からの情報はホルモンの分泌に関係します。光の刺激が目に入ると脳を興奮させ、ホルモンバランスを悪くするのです。
成長ホルモンは夜間の深い睡眠中に分泌されるので、就寝時刻はできる限り21時頃までを目指し、朝早く起きて日の光を浴びることが大事です。セロトニンと呼ばれるホルモンは、光と朝食で(魚や卵などトリプトファンを欠かさずとることで)腸の中でつくられます。
ハッピーホルモンと呼ばれるセロトニンは、やる気や集中力を上げ、日中は元気脳の源として働きます。さらに、夕飯にマグネシウム食材をとることで、メラトニンという睡眠を促すホルモンになります。メラトニンは睡眠中に出る成長ホルモンの分泌を促し、身長を伸ばすのに大きな役割を果たすものです。
朝起きる時間から夜の睡眠まで、1日の「よい循環」をマネジメントできたら最高です。メジャーリーグの大谷翔平選手は「1日12時間寝る」という話もあり、「寝る子は育つ」は本当ですね。
③ 適度な運動

身長を伸ばすためには、適度な運動も必要です。
運動によって骨端線が刺激され、成長ホルモンの分泌が促されることになるからです。運動する子は、常にかかとから骨刺激を与えられるため背が伸びる可能性が高まるのです。
ただし、筋トレなど激しいトレーニングをしすぎたり、小さいうちから筋肉をつけすぎたりすると、筋肉は固く重くなり、伸びようとする骨端線に早く限界がきてしまうことになります。
④心の健康
ストレスや不安が少ない状態を保つのも、身長を伸ばすためには大事なことです。今の子どもたちは塾や習い事で忙しく、余裕のない時間がストレスとなり、体のバランスが崩れがちです。そうなると成長ホルモンの分泌が少なくなる可能性があります。
遊びの時間やリラックスできる時間を十分に確保することも大事です。
また、大人が家で疲れていたり、不機嫌だったりする姿を見せてしまうと、それが子どものストレスにつながる場合もあります。子どもは親の感情を見抜きます。
毎日短い時間でもお子さんと会話し、お子さんの話を聞いてあげることで、愛情を伝えてあげてください。家庭で安心して過ごせる環境を整えることで、お子さんはのびのびと過ごすことができ、それが成長ホルモンの分泌を促すことにつながるのです。
■身長を伸ばすための生活習慣まとめ
・朝ごはんを抜かない。朝からタンパク質とお米を食べて、カロリーをしっかりとる
・甘いもの、甘いジュース、スナック菓子は、避ける工夫を
・睡眠時間を確保し、スマホ時間で脳疲労を起こさせないように
・親が「疲れた」「忙しい」を連発せずに、明るい環境を整えて (ネガティブな言葉は子どもの脳を萎縮させます)
優しさの中に、しっかりルールを作ってください。
身長を伸ばすためのQ&A
ここでは、子どもの身長について保護者の方からのよくある質問とその回答をご紹介します。
Q 「男の子と女の子で伸びるタイミングが違う?」
A 女の子は成長期が早く来るため、小学校高学年の頃は、クラス全体で女子のほうが高身長ということもよくあります。一方、男の子は中学に入ってからが成長ホルモンを分泌させて身長を伸ばす勝負となるので、小学生での身長はあまり気にしなくても大丈夫です。逆に女子は3年生ぐらいから高学年にかけての時期が大事なので、この間の食事や生活をしっかりサポートしていきましょう。
Q 「牛乳は毎日どれくらい飲んでいいの?」
A 日本人は、その約4割が乳糖不耐症と言われていて、下痢や腹痛などトラブルを起こすことがあります。その場合は牛乳を飲むのは避けてください。お子さんの腸の状態が大丈夫ならば、1日にコップ2〜3杯程度がよいでしょう(生産者が見える牛乳はカルシウムの吸収がよいです)。飲みすぎると牛乳貧血になる場合があります。
乳糖不耐症の場合は、カルシウムリッチなおやつとしてチーズを代替食品にするのもおすすめです。
Q「どんなスポーツが身長を伸ばすのにプラスに働くの?」
A 縦方向へのジャンプ動作は身長を伸ばす刺激になります。縄跳びやバレーボール、トランポリンなどは、骨に刺激を与える動きが多いものなので、おすすめです。
また、ラジオ体操、水泳など全身を使う運動は血行を促進し、成長に必要な栄養の摂取やホルモン分泌の助けになります。
さらに、朝は一番身長が高いので、朝起きた直後や寝る前のストレッチは背骨や関節の柔軟性を高め、姿勢改善にも効果的です。
ダンスのように、好きな音楽を聴きながら楽しく取り組める運動もよいでしょう。
Q「姿勢が悪いと身長に影響はあるの?」
A 現代の子どもたちは、スマホやゲームなどの影響で猫背だったり、しっかり立つ姿勢が苦手だったりします。骨と骨の関節がつぶれ、ゆがみが発生する恐れもあります。O脚や猫背のまま背が伸びるとしたら残念ですね。姿勢が悪いと筋肉や骨格のバランスが崩れ、実際に身長が伸びる可能性が失われます。親がよい姿勢を保ち、お手本を見せることも大切です。
最後に~親の一番の仕事は「身体づくり」
小学生であれば、自分の身長のことをあまり気にかけていないお子さんも多いことでしょう。正しい食事や生活習慣は成長してからも役に立ちます。今しかできない成長期に、食の大切さを伝えることはとても大切です。時間がない大人の事情で、甘いものやスナック菓子などを食べさせていると、味覚を変えるのが難しくなります。そのため、なぜ食生活や生活習慣を改善する必要があるのかを、お子さんにもよく理解してもらうとよいでしょう。
例えば、「どのくらい身長があるとうれしいか」「どんな人になりたいか」「憧れの人はいるか」など、親子で話し合ってみるといいと思います。ご両親の理想ではなく、お子さん自身が自分の身長を伸ばしたいと考えることが大切です。そのために何が必要か? どうしたら目標に届くか?など、常に目的をもって、どうしたらそこに到達できるかを一緒に考えられる家庭だと素敵ですね。
家庭は社会の最小単位。子どもが社会で自立するための生活習慣を意識して過ごしていきたいものです。子どもは大人の習慣を真似します。姿勢や間食など、親が自分ではできていないことを子どもに求めると、反抗的にもなります。保護者の方の一番大切な仕事は、お子さんの身体づくり。身長をテーマとするならば、タイムリミット(ゴール)があることで、成長期の課題は明確です。
「親の身長が低いから」という思い込みは可能性を狭めます。ただし一方で、努力しても理想的な身長にならないこともあるでしょう。学校の試験と一緒で、お子さんの価値を数字で決めつけず、「そうなったらすごいね」と明るく声をかけてあげてください。一緒に栄養価の高いレシピを考えて作ったり、プロセスを楽しむことが大切です。大切な宝物であるお子さんの生活習慣をサポートしつつ、見守っていただけたらと思います。
この記事の監修・執筆者

タレントスカウトから新人の現場マネージャとして全国、海外で仕事に従事後、スタイリストとして起業。
バブル期の過労で体調を壊し、自然治癒の学びを分子整合栄養学にて自分自身の体調管理に没頭しながら学ぶ。
金子雅俊氏に師事を受け、日本に広めた血液から読み解く栄養学、分子整合栄養学アドバイザーの資格を得る。
多くの人の相談から不調の原因を追究し、データを基に個体差で体調管理のアドバイスを行う。
個人のパフォーマンスを最大限に伸ばすための栄養対策、バイオリズム等を提案。
現在、さまざまな講演活動、医療や検査のマネージメント、パーソナルコンサル、講座を実施している。
【主な著書】
『卵を食べれば全部良くなる』(マガジンハウス)
『男は食事で出世させなさい』(ポプラ社)
『身長を伸ばす7つの習慣』(主婦の友社)
『その不調、栄養不足が原因です』(主婦の友社)
こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪








![【遺伝だけでは決まらない!】子どもの身長は間違いなく栄養で伸ばせます[身長先生/医師・田邊 雄]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/03/pixta_73435392_M_Rign-700x467.jpg)













![【すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり!】素材のおいしさを引き出す「シンプル蒸し」レシピ3品[りよ子]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/canvaaikyacchi-1_ZhYH-700x466.jpg)







![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-1024x683.jpg)