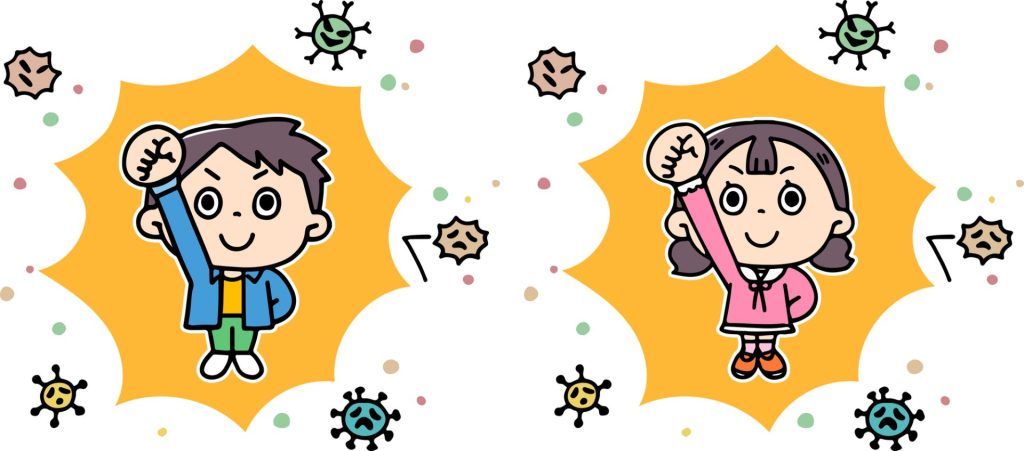多くの保護者が抱えている「子どもが野菜を食べてくれない」という悩み。健康や成長に悪影響を及ぼすのではないか……と不安になりますよね。
そこで今回は栄養学の視点から野菜を食べる必要性と、「野菜嫌いは克服すべきなのか」を考えます。
監修・文/相馬琴寧(管理栄養士)
子どもが野菜を嫌うのはどうして?

そもそも、野菜は子どもに嫌われがちな食材です。保護者の皆さんも、「子どもの頃はあの野菜が苦手だったなあ…」と思う方は多いのではないでしょうか。
これにはさまざまな理由があると考えられています。
体に悪いものだと認識してしまうから
子どもが野菜を嫌う一番の理由は、味や食感、野菜の持つ独特の風味です。本来、苦味や酸味は、毒や腐敗した食べ物を感知するシグナルです。また、それらは食感や未知の風味からも感じ取ることができるものです。
感覚が鋭敏な子どもが、これらを「体に悪いものだ」と直感し、食べない判断をすることはとても自然なことなのです。
強い苦みを持つピーマン、ぐにゅっとした食感のナス、独特の風味を持つニンジンやセロリなどが子どもに嫌われやすいのもこういった理由からです。
未知の味や風味を「有毒かもしれない」と警戒することは、決して悪いことではありません。
子どもが本能的に野菜を警戒し、結果的に「嫌い」になってしまうことは、生物としてとても自然なことなのです。
「味蕾」の数が多く味を感じやすいから
また、子どもが野菜を嫌うのには、体のつくりにも理由があります。
人間の舌には、味を感じる舌の器官である味蕾(みらい)があります。実は子どものほうが大人よりも味蕾の数が多く、味を敏感に感じ取ることができるのです。
そのため、子どもは大人よりも敏感に苦味などを感じ取ってしまうと言われています。大人になるほど味蕾は減りますので、苦味などを感じる力は弱まっていきます。これが大人になるにつれ野菜を克服できる一因であると考えられています。
野菜を食べるメリット 野菜から摂れるビタミンのお話

野菜を食べることで摂取できる栄養素は、ビタミン、ミネラル、食物繊維などが挙げられます。この中でもビタミンは、他の食材にくらべて野菜から摂ることが多い栄養素です。では、子どもにとって重要なビタミンはどのようなものなのでしょうか。
子どもにとって大切なビタミンとは
ビタミンとは、ヒトが必要とする有機(炭素を含む)栄養素のうち、微量かつ体内で合成できないものを指し、現在では一般に13種類が存在すると考えられています。
| 主な役割 | 多く含まれる食品の例 | |
| ビタミンA | 暗所での視力の維持、免疫系の維持 | レバー、うなぎ、卵、 にんじん、ほうれん草 |
| ビタミンD | 骨の形成を助ける | きのこ類、魚類(鮭など) |
| ビタミンE | 細胞膜の一部に存在、酸化の防止 | 卵、大豆、ナッツ類、魚類かぼちゃ |
| ビタミンK | 血液凝固、 骨の形成を助ける | 納豆、海藻類、ほうれん草 |
| ビタミンB1 | 糖からのエネルギー産生を助ける | 豚肉、大豆、うなぎ、そば、玄米、ブロッコリー |
| ビタミンB2 | 脂質からのエネルギー産生を助ける | ブロッコリー、ほうれん草、牛乳 |
| ナイアシン | 皮膚や粘膜の健康維持 | カツオ、鶏肉、きのこ類 |
| ビタミンB6 | タンパク質の代謝を助ける | カツオ、バナナ、さつまいも、赤パプリカ、ブロッコリー |
| ビタミンB12 | 赤血球の形成を助ける | 肉類、魚類、貝類、卵 |
| 葉酸 | 赤血球の形成を助ける | ブロッコリー、枝豆、ほうれん草 |
| パントテン酸 | 皮膚や粘膜の健康維持 | レバー、きのこ類、牛乳 |
| ビオチン | 皮膚や粘膜の健康維持 | 卵、落花生、大豆 |
| ビタミンC | コラーゲン形成を助ける、皮膚や粘膜の健康維持、酸化の防止 | 赤パプリカ、ブロッコリー、かぶ、アセロラ、キウイ |
この中でも特に子どもにとって重要なのは、ビタミンDとビタミンKの2つ。
表にもあるように、この2種類、とりわけビタミンDは骨が作られる過程で重要な役割を果たす栄養素です。子どもが強い骨を作るために必要なものです。
ビタミンDは、きのこ類や魚類に多く含まれる栄養素です。お子さんが食べられる食材を見つけて楽しく摂取して、大きく成長する時期の栄養を支えてあげるようにしましょう。
野菜が一番ビタミンをバランスよく摂ることができる!
野菜はどれか特定のビタミンが多いのではなく、満遍なくさまざまな種類が含まれています。そのため野菜は、ビタミンをバランス良く、不足なく摂取するのに最適と言えます。
多くの食品からビタミンをバランス良く摂取しようとすると、献立作りもかなりの負担になってしまいますので、野菜を取り入れられるととても便利です。
子どもが野菜を食べなくても大丈夫?

ビタミンは野菜からしか摂れない?
子どもに必要なビタミンがわかったところで、本題に移りましょう。これらのビタミンは野菜からしか摂れないのでしょうか? 結論から言えば、そんなことはありません。
例えばビタミンB1は玄米や豚肉に、ビタミンCはアセロラやキウイなどの果物に非常に多く含まれており、その量は野菜以上であることもしばしば。そして実を言うと、野菜にほとんど含まれていないビタミンも存在します。ビタミンB12(肉や魚、卵などの動物性食品にのみ含まれ、野菜には含まれない)やビタミンD(キノコ類や魚類に含まれ、野菜にはほとんど含まれない)がこれにあたります。
野菜を食べさせようと無理しなくても大丈夫
ビタミンは身体に必須の栄養素です。不足すると身体は不調に陥り、特定の栄養素が特に欠乏すると、特異な病気の症状があらわれることも。
しかし、前述したようにビタミンは野菜以外からも摂取できる栄養素です。野菜を食べられないことが、ビタミンの不足に直結するとは限りません。野菜が食べられない=今すぐに絶対体調を崩す、と悪い方向に考えなくても大丈夫です。
つまり、ビタミン不足の観点から言えば、野菜を無理に食べさせる必要はありません。お子さんが野菜をあまり食べられなくても、思いつめなくて大丈夫。時には「野菜を食べさせること」をお休みする機会を設けながら、無理のない量や頻度を少しずつ試していけるといいでしょう。
それでも野菜嫌いの子どもが心配! そんな保護者の方に
果物や野菜ジュースを使いましょう
そうは言っても、好き嫌いは減らしておきたい、野菜嫌いは克服しておきたいという方もいますよね。そんな方は、ビタミンAとビタミンCだけでも摂れていればOK!と考えてみてはいかがでしょうか。野菜から摂取する割合が高いこの2つの栄養素を、果物などほかの食材でまかなうのです。
果物に慣れてきたら、野菜と混ぜてしまって「フルーツサラダ」にして食べることで、野菜に対する抵抗感を無くせることも。フルーツサラダは切って和えるだけでできるので、子どもといっしょに作ってみるのもいいですね。

お好みの野菜とフルーツをぶつ切りにして、ドレッシングやタレで和えます。
おすすめの調味料はにんにく塩だれ!
その他には、野菜ジュースの活用も一つの手です。野菜ジュースはビタミンAやビタミンC、その他野菜に含まれる栄養素を豊富に含んでいます。どうしても子どもが野菜を食べなくて不安という場合は頼ってしまいましょう。ただし、あくまで「ジュース」ですので、糖分が高いことはお忘れなく。糖分を摂りすぎないよう、野菜ジュースを飲んだ日はお菓子を控えめにするなどの配慮をするとより良いでしょう。
まとめ
野菜嫌いは今すぐ克服しなくてもOK!
子どもが野菜を食べないことに不安を感じている保護者の方は多いと思います。しかし、野菜からバランスよく摂取できるビタミンは、果物やその他の食品から補うことができます。
そして、今野菜が嫌いで食べられない子も、味蕾の減少や、多くの食材との出会いにより、成長とともに少しずつ食べられるようになることが多いと言われています。ここまでご紹介してきたように、栄養学の観点からは「無理して今すぐに治さなくても大丈夫」です。焦りすぎず、ゆっくり見守ってあげてください。
家族で重ねていきたいポジティブな「食経験」
野菜に限らず、人が食べ物を食べるのは、「栄養素を身体に取り込むため」だけが理由ではありません。ご飯を食べることは生活のリズムや、家族や友人とのコミュニケーションを作り、脳や身体にさまざまな好影響をもたらします。そしてそもそも、ご飯を食べて「おいしい!」と思えることは、多くの人にとってとても幸せなことですよね。
このような、食事を通して生まれた感情、得た知識、思い出など、全てをひっくるめて「食経験」と言います。
食事は人生そのものと密接に関わっています。食経験が豊かであることは、人生を楽しく生きる一助になるのではないでしょうか。子どもには嫌われがちな野菜ですが、野菜を食べて「美味しい」と思うことも「まずい」「嫌だ」と思うことも、とても大切な経験なのです。
ただ、「まずい」「嫌だ」と思った経験は、あまり増やしたくはないですよね。ですので、ネガティブな食経験はほどほどに、子ども、そして保護者の方も、無理のない範囲で「おいしい」「楽しい」といったポジティブな食経験を増やしていくようにしましょう。

こそだてまっぷから
人気の記事がLINEに届く♪






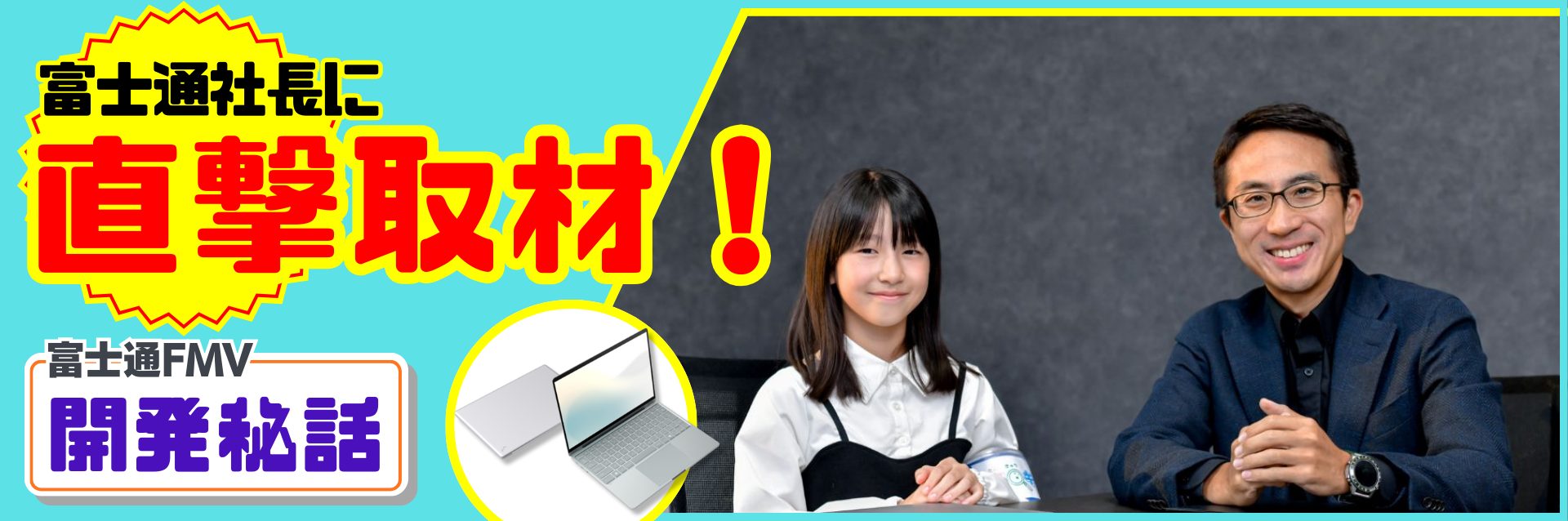



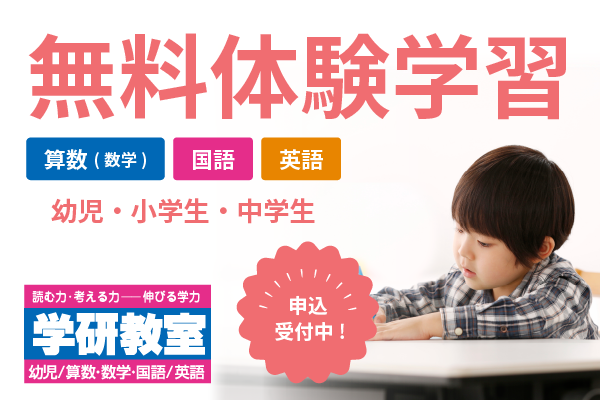










![【すべてを蒸したい せいろレシピ、おかわり!】素材のおいしさを引き出す「シンプル蒸し」レシピ3品[りよ子]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/canvaaikyacchi-1_ZhYH-700x466.jpg)







![【SOSが出せない、自分で決められない…】「指示待ちっ子」を卒業させる、親の習慣10[専門家監修]](https://kosodatemap.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/pixta_121483898_M_tlOn-1024x683.jpg)